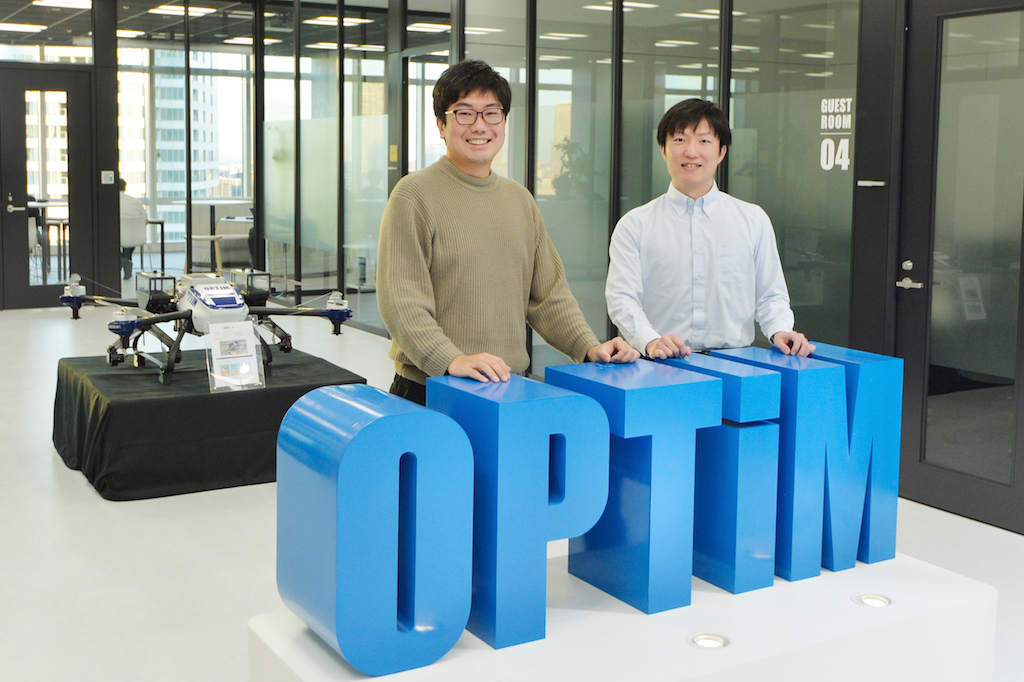地理的制約のない上空からのアプローチ
ドローンで農業は飛躍的に進化する。オプティムが目指す「第4次産業革命」
これからの市場で注目を集めそうなトレンドを深掘りする連載「マネ部的トレンドワード」。ロボティクス・ドローン編2回目の本記事では、オプティムを取り上げる。
さまざまな領域で活用が進むドローンだが、一段とニーズが高いのが「農業」だ。オプティムも、ドローンやそれを活用した農業ソリューションを提供。さらに、これらのサービスを農家に無償提供し、出来た作物を全量買取する「スマートアグリフードプロジェクト」を始めている。
農業でのドローン事業やスマートアグリフードプロジェクトについて、オプティム ビジネス統括本部 農業事業部 ゼネラルマネージャーの大澤氏と、同本部 ロボティクス事業部 マネージャーの長谷川氏に聞いた。
機体開発からサービス提供まで。オプティムのドローン事業
農業におけるオプティムのドローン事業は、大きく3種類ある。1つは同社で機体開発から行った固定翼ドローン「OPTiM Hawk V2」だ。
私たちがよく見るドローンは複数のプロペラがついた「マルチコプター」だが、こちらは固定翼であり「飛行効率が高く、マルチコプターに比べて同じエネルギーで長時間飛行できる」と長谷川氏。機体にカメラを搭載し、大規模な圃場(ほじょう:田や畑などの農地)などを空撮する。
「自治体等では、国の経営所得安定対策等交付金の支払いのため、圃場で栽培されている作物を確認する『作付け確認』という作業があります。私たちは、このドローンで大規模な圃場を空撮するのに加え、その画像を解析して申請通りの作物が栽培されているかを確認するサービスを提供しています」(長谷川氏)
開発したドローンを外販するのではなく、それを使った画像解析サービスまで行うのが特徴。ある自治体では、約8500ヘクタールの大規模圃場に導入し、今まで人手で21日かかっていた現地確認が2日で済んだことも。飛行可能時間は約90分とのことだ。
2つ目の事業は、外部メーカーのドローンとオプティムの解析ソフトを連携させたり、アタッチメントを搭載し、その機能を使ったサービスを提供する形。例として、ドローンによる直播(ちょくは)や、ピンポイント農薬散布や作物の生育状況の画像解析などがある。
最後に3つ目の事業が、国産ドローンの開発や運用支援だ。NTT東日本、ワールドリンクと合弁会社「NTT e-Drone Technology」を2021年1月に設立した。
3つの中でも面白いのが、アタッチメントを使った事業だ。特徴は、装置を提供するだけでなく、その機能を使った解析や実行までオプティムが行うこと。
たとえば、同社が開発した「ドローン搭載型播種機(はしゅき)」。米を育てる際、通常はある程度成長した苗を田に植えるのが一般的だが、それ以外に、米の種子(種籾:たねもみ)を直接田んぼに播いて育てる「直播」という方法がある。
「我々の開発した播種機は、上空からドローンで種子を打ち込みます。とはいえ、単純に地表に落としても根付きませんし、打ち込みが浅いと成長時に稲穂の重さで倒れるので、十分な深さで地中に打ち込む技術が必要。また、種子を打ち込む間隔が狭すぎたり量が多すぎたりすると“密植”になり、生育不良や病気の原因に。品種や地域に合わせて狙ったところへ適正な量の種子を打ち込める機構を追求しました」(長谷川氏)
この“適正な打ち込み”を実現するため、「何度も何度も研究機関と検証を重ねた」と話すのは大澤氏。なお、外部の機関と研究しながら技術を確立するスタイルは播種機に限った話ではない。たとえばドローンの画像を使った作物の生育状況の分析でも、農薬散布でも、作物や栽培の知見が必要になる。
「大学や行政の研究機関、食品や農機のメーカーの方々と、さまざまなテーマで技術研究のプロジェクトを進めてきました。これまでに70以上のプロジェクトを行いましたが、全てが社会実装できるわけではありません。播種機は成功例の1つです」(大澤氏)
日本の離農者の多くは中山間地域や小さな農地の保有者など、機械が入りにくいような「作業効率の上がりにくいエリア」だと大澤氏。そういった場所こそ、地理的な制約なく上空から作業できるドローンを使えれば「飛躍的に効率が上がります」と続ける。
農家に技術を提供し、出来た作物を全量買取するプロジェクト
こうして出来た同社の技術を、農家に無償提供するのがスマートアグリフードプロジェクト。播種機のほか、ドローンによるピンポイント農薬散布など、AI・IoT・ロボティクスを活用した技術を契約生産者に提供。そうして出来た作物はオプティムが全量買取して流通を担う。
「生産者の方が先端技術を使うだけで終わらず、出来た作物に付加価値がつくことが重要。我々の技術が生産者の所得向上に寄与できれば、社会実装に近づきます。そこで私たちが全量買取し、ネットでの直販や業者間流通で作物を売る、生産者の所得を上げるところまでを担う形です」
農業にテクノロジーを持ち込む取り組みは、近年「スマート農業」といわれる。大澤氏は、それによって「農繁期における課題を解決したい」と口にする。
「農業は繁忙期が収穫シーズンなどの短期間に集中します。こういった“農繁期”の負荷が高いため、小規模な農家や高齢農家は継続が難しく農業をやめてしまう現状があるでしょう。農作業を効率化・最適化することは、地域の農家の持続可能性も後押しするはずです」
今回の記事では農業分野の話に特化してきたが、オプティムでは、AI・IoT・ロボティクスを建設や医療などさまざまな分野に掛け合わせた事業を行っている。同社が目指すのは「第4次産業革命をリードすること」(大澤氏)だ。
2000年に創設され、モバイルデバイスマネジメントという、たくさんのモバイル機器を一括管理するソフトウェアサービスでシェアNo.1も獲得した同社。その後、ここまで多角的に事業を展開できた要因は、積極的な研究開発にあると2人は考える。
その証左として、2020年1月に発表された日本経済新聞の調査では、売上高100億円以下の中堅上場企業「NEXT1000」の中で、過去3年の売上高研究開発費比率の平均首位がオプティムだったという。こういった開拓の姿勢が、農業の取り組みにも表れていることは明らかだ。
テクノロジーを使い、農業を進化させる。その歩みの先には、第4次産業革命を本気で起こそうとする強い意志がある。
(取材・文/有井太郎 撮影/森カズシゲ)
※記事の内容は2022年12月現在の情報です
関連リンク