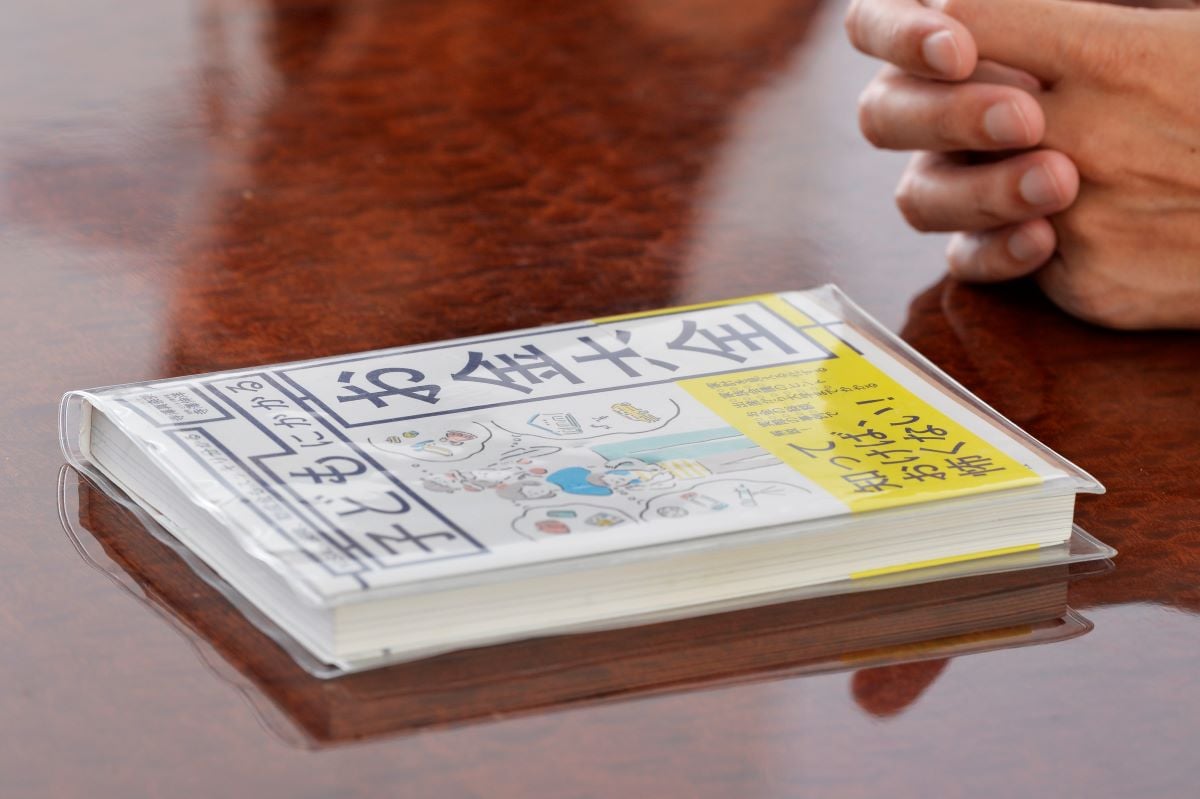“お金のプロ”夫婦に聞く「子どもにかかるお金」の話
子どもが産まれ、夫婦2人の生活から家族の生活へと変わり、家庭が形づくられていく。そんな将来を考えるとワクワクしてくるが、思い描いた幸せや希望を叶えるには、お金の力を借りる必要があり、いままでになかった悩みを抱く人も多いだろう。教育資金の備え方を解説した1冊『NISA、保険、助成金もスッキリ分かる 子どもにかかるお金大全』には、次のように書かれている。
「子どもの誕生によって『出費は跳ね上がるのに、収入はがくんと落ちるかゼロになる』――これこそが、子どもに関連する最大の悩みになる」
子どものための教育費や食費、日用品費は増える一方で、産休や育休、時短勤務などを利用すると収入は減るという現実が待っているということだ。では、どのようにお金の悩みを乗り越えていけばいいのだろうか。この書籍の著者である“お金のプロ”夫婦、ファイナンシャルプランナーの寺澤真奈美さんと投資・ビジネス書作家の寺澤伸洋さんに聞いた。
SNS社会に生きる親が抱いてしまう“焦燥感”
「子どもに関する費用のなかでも特に金額が大きい『教育費』は、幼稚園から大学まですべて国公立に進んだ場合でもトータルで1000万円かかるといわれています。高校・大学が私立(大学は私立文系)の場合は1400万円、中学校から私立に進む場合は1700万円、小学校から私立に進む場合は2500万円ほどという試算がありますが、これはあくまで相場で、習いごとなどを厳選した場合と考えましょう」(真奈美さん)
かかってくるのは学費だけではない。塾や習いごとに通わせれば通わせるだけ教育費は上がり、生活費も思いがけず高額になりやすいという。かつて上京組の大学生は賃料の低い学生寮に入るのが一般的だったが、現在は学生寮を使わずに質の高いマンションなどを借りる学生が多いといった例もあり、親の負担が増える可能性がある。
「現代の子育て世帯を見ていると、『人と比べてお金がない』『周りがやってるから子どもに中学受験させる』のように他人基準で判断している方が多いように感じます。SNSが普及して得られる情報が増えたからだといえますが、それによって教育費も積み重なっているのだと思います」(真奈美さん)
「『この地域ではみんなが中学受験させているから、受験させたほうがいい』というレールに乗ると、ここまできたらやるしかないという気持ちになってしまうのでしょう。また、本当にそれが子どものためになっているのかが明確に見えないため、不安感や焦燥感を煽られるのだと思います。私たちも子どもを育てる親なので、何かのきっかけでレールに乗るかもしれませんが、子どもや家族のためになるのかという点はきちんと考えたいですね」(伸洋さん)
まず行うべきは「夫婦間での現状の把握」
真奈美さんと伸洋さんも、大学生と中学生の子どもを育てるママとパパ。いままさに子どもにかかるお金と向き合っている2人が、生活において大切にしていることとは。
「夫婦で現状を把握することですね。2人でキャッシュフロー表を付けて、自分たちの収入や生活費、これからの想定なども含めて把握することが大切だと考えています。例えば、子どもが成人するまでのお金の流れを俯瞰して捉えると、備えるべき額が見えてくるので、漠然とした不安を解消することができます。夫婦間の透明性は重要です」(真奈美さん)
ファイナンシャルプランナーとしてお金に関する相談にも乗っている真奈美さんは、「共働き世帯が増えたことで、互いにいくら持っているか知らない夫婦は増えているように感じる」と話す。また、共働きならではの問題として、夫婦の収入差が挙げられるという。
「夫婦2人の頃は互いに同じくらいの収入だったとしても、妻が何度か出産をすると産休・育休や時短勤務で収入が減ったり、場合によっては離職・転職をして環境が変わったりすることもあります。一方、夫は変わらず働き続けるので収入差が生まれるにもかかわらず、以前と同じルールで生活費や教育費を折半している家庭もあります。そうなると女性は貯金ができず、将来への不安ばかりが膨らむという悪循環に陥ってしまうのです。子どもができてから改めて夫婦で現状を共有し、互いの状況に合わせて調整できる関係が理想的ですよね」(真奈美さん)
夫婦の片方が働き、片方が専業主婦(主夫)となっている家庭では、別の問題が生じる可能性があるという。
「ここでは夫が労働者、妻が主婦と仮定します。かつては働く夫が妻にすべての収入を預け、妻が管理するという家庭が多いイメージでしたが、最近は働く夫が収入を管理して、妻に生活費だけ渡す家庭も増えている印象があります。このケースはかなり難しく、子どもの大学進学費用などの大きな出費を控えているときに、妻は全体の収入を把握していないので計画が立てられません。夫は日々の支出を把握していないので、費用感がつかめていない。夫婦の認識のズレが生まれやすいのです」(真奈美さん)
共働きであれ片働きであれ、夫婦ともに現状を把握しておくことは重要ということだ。
「自分も配偶者も子どもも健康という前提で将来を考えてしまいますが、事故にあったり病気になったりする可能性がないとはいえません。私自身も妊娠中に入院し、離職せざるを得ない状況になった経験があるように、意図せず収入が減ったり働けなくなったりすることもあります。将来に対する不安はたくさんあるので、数字で明確に見通せるお金のことくらいは夫婦間で共有しておくと、多少は生活もスムーズに進むのではないかと思います」(真奈美さん)
「家計簿」は日々の収支を可視化するためのツール
いまでこそ夫婦で情報を共有しているという寺澤夫妻だが、もともと真奈美さんは家計簿を付ける習慣がなかったそう。
「2人で共通の家計簿を付け始めたのは、第一子が産まれるちょっと前くらいでした。子どもが産まれるという変化を前にして、お互いにちゃんと把握しておかないといけないよねって話になったんです。僕はもともと家計簿を付けるのが好きだったんですが、妻はレシートを溜めてしまうタイプでした(笑)」(伸洋さん)
家計簿を付けるだけでも日々の収入や支出が可視化され、どこにお金をかけるべきか、どこの支出を削減するべきかという判断がしやすくなるとのこと。
「私はもともと『家庭をつくるなら家や車が欲しい』と考えていました。もし、車を持っていたとしても、当時は平日9時から17時まで働いていて、車を使っても土日だけ。職場もスーパーも徒歩圏内だったので、車の購入費や駐車場代などを計算して、必要ないという結論に至りました。いまは週1くらいでカーシェアを利用しているんですが、結構乗ったと感じても利用料は月2万円くらい。年間24万円。車を購入した場合と比べると、圧倒的にコストを抑えられています」(真奈美さん)
「支出を可視化すると、月々の金額に12をかけて、さらに10をかけるというクセがつきます。例えば、スマホを格安スマホに変えて料金が月5000円減るとしたら、12カ月で6万円、10年で60万円節約になることがわかるんです。『ひと月5000円』だけを見ると払ってもいいかと思うかもしれませんが、長い目で見たときの価値を考えると判断しやすくなります。『×12×10』を意識してみてほしいですね」(伸洋さん)
大切なのは、夫婦で現状を把握し、「この支出は本当に必要なのか」と話し合うこと。このステップを踏むことでお金に関する悩みが解消し、子どもにかかるお金も備えやすくなるだろう。次回は、お金を備えるための方法を寺澤夫婦に伺う。
(取材・文/有竹亮介 撮影/森カズシゲ)