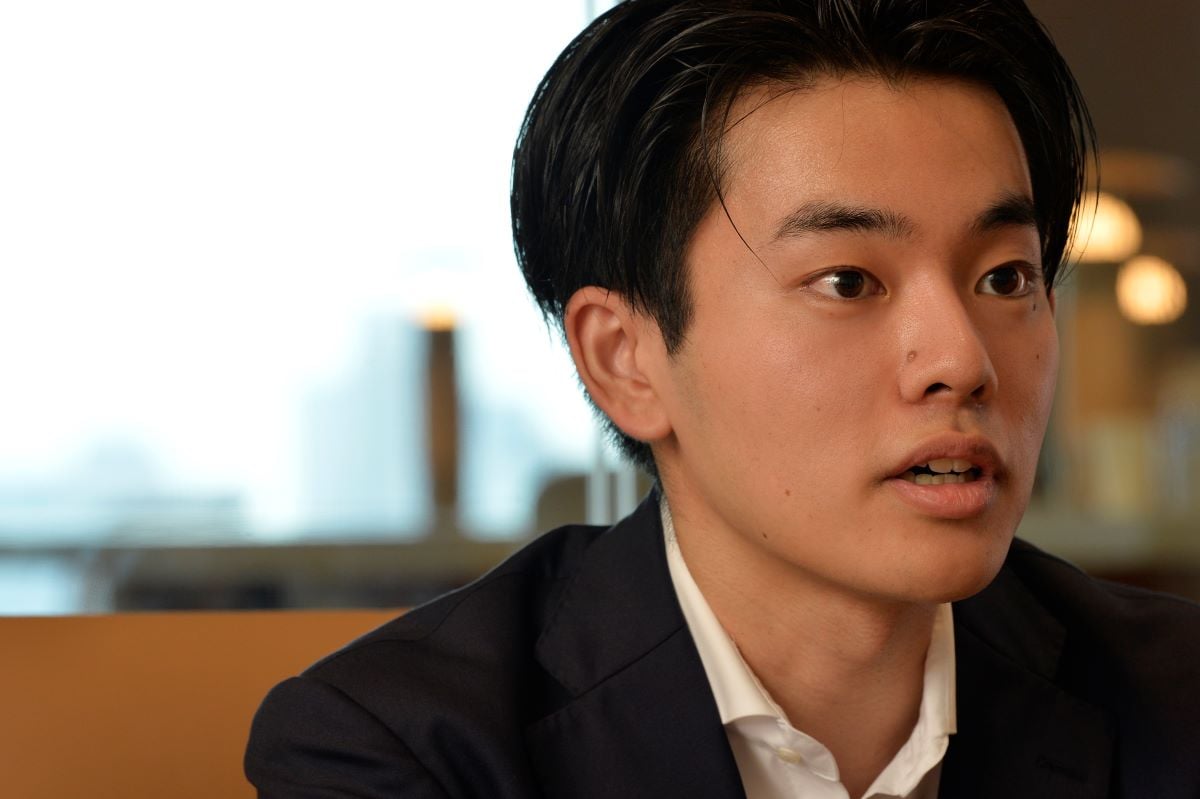若き視点で考える、日本で期待できる投資テーマ
「進化の探索」で成長銘柄を見つける、25歳の“ひふみ”ファンドマネージャー・松本氏は企業の何を見るのか
- TAGS.
米国株やオルカン(オール・カントリー:全世界株式)が話題になる中、「日本株の魅力」はどこにあるのか。これから期待できる国内の産業や投資テーマはあるのか。こうした質問を“日本株のスペシャリスト”にぶつける連載「ニッポン、新時代」。今回お話を聞いたのは、25歳という異例の若さでファンドマネージャーに就任したレオス・キャピタルワークスの松本凌佳氏だ。
「君がこの新しいファンドの歴史を作っていくんだよ」。人気の投資信託「ひふみ」シリーズを長年運用してきた藤野英人氏(レオス・キャピタルワークス代表取締役社長 CIO)にそう言葉をかけられ、同社の新たな投資信託「ひふみクロスオーバーpro」のファンドマネージャーに抜擢された松本氏。次代の担い手は、日本株のこれからをどう見ているのか。大切にする「銘柄の探し方」はあるのか。本人に尋ねた。
着目しているのは、大胆な「新卒給与の上昇」
自身の強みを聞かれて、「会社の成長モデルや経営戦略が最終的にどう数字として表れるのか、そのつながりを考えられるところです」と答えた松本氏。もともと大の数字好きで、高校卒業後は東京大学の理科一類に入学。統計学などを深く学び、データを読み解くことを得意にしてきた。
一方、大学3年以降は経済学部に進んだ。統計と経済に触れたことにより、その2つをつなげて「企業の戦略をロジカルな要素に落とし込んで投資判断できる」という強みが身についたという。
たとえば経営者が口にした方針や大きなビジョンが、企業が持つあらゆる数字のどこに作用するか。あるいは、社長交代といった事象が及ぼす数字的な変化を予測するなどだ。
異例の早さでファンドマネージャーとなった松本氏だが、その話が来た時はもちろん迷ったという。「まだキャリアが浅く、この業界に来て3年目の自分に、何年も先を見据えた企業投資ができるのか不安がありました」。だが投資信託は一人で運用するものではない。藤野氏をはじめ、素晴らしいチームの中で働けると考え、長い検討の末にそのポジションへの挑戦を決断した。
「25歳のファンドマネージャー」というと華々しく聞こえるが、本人は「学ばなければならないことが山ほどある」という事実も冷静に受け止めている。この取材で、近年の日本株の動きについて聞いた時も、そんな一面を覗かせていた。
「私は1999年生まれで、物心がついたのは2011年あたり。その時期から現在まで、日本株は長期の上昇トレンドを続けてきました。つまり私自身、長い停滞や下落を経験したことがまだないんです。ファンドマネージャーとしては、日本株にそういう時代があったことを知っておく必要がある。今はさまざまな方に当時のお話を積極的に聞いていますね」
なお、短期で見ると、2024年夏以降は日本株が乱高下するケースが多くなった。こうした中で投資家はどう振る舞えば良いのか。「株価の上下だけで判断せず、企業の本質的な価値が変動しているのかを確認することが重要ではないでしょうか」。
人はどうしても目に見える数字を過剰に意識しやすい。値動きに振り回されず、「たとえば自分がその銘柄に投資している理由に変化がないかを考えてほしい」と話す。
さらにこれからの日本株においては、松本氏が注目している数字がある。新卒における給与の上昇だ。「何年にもわたり変化が見られなかった企業でも、近年は数万円単位で上がっているケースがあります。ここから派生して、さまざまな動きが長期的に起きてくるのではないでしょうか」。
次の銘柄探しに有効な「進化」の探索
松本氏は、2022年に新卒でレオス・キャピタルワークスに入社すると、アナリストとして国内外の中小型株を中心に企業調査を行ってきた。
2024年からは、新たな投資信託「ひふみクロスオーバーpro」のファンドマネージャーに就任。この投資信託は、未上場株と上場株の両方に投資するもので、上場前から企業の成長ストーリーに関与し、日本のスタートアップが上場後に伸び悩む“死の谷”の解消を目指すという。
その運用を担う松本氏は、これからの日本で注目する「投資テーマ」や、自身の「銘柄発掘の極意」をどう考えているのか。まず前者については、人手不足における工場作業の「自動化」を挙げる。
「工場見学に行くと、物流倉庫の自動化は顕著に進み、人の作業をロボットが代替する領域においても、ソフトウェアが進化してできる作業が格段に増えています。これにより工場などの一人あたり生産性は如実に上がっていますし、これからの上昇余地も多分にあると考えています」
後者の「銘柄発掘の極意」についても聞いてみたい。次の投資先を探す時、どのようなポイントを見れば良いのか。「私がまず意識しているのは、その企業を前回見た時と比較して、少しでも進化や成長があるかを確認することです」。
「業績面などの数字的進化はもちろん、感覚的な進化も大切です。飲食店でいえば、以前来店した時よりおいしくなっている、メニューが増えている、従業員の動きに余裕が出ている、など。デジタルサービスでいえば、ボタンが減って操作性が良くなった、あるプロセスが簡単になったなど、いろいろなケースがあるでしょう」
そうして見つけた感覚的な進化が、「いずれ業績などの数字に現れることもあります」とのこと。「個人投資家の方も実践しやすい方法ではないでしょうか」と話す。
転職に使えるほど充実したIRは「日本市場の魅力」
日本の株式市場の“魅力”は何かと尋ねられて、「上場企業が多く、さまざまな分野に多様な銘柄があること」と答える松本氏。ニッチトップ企業や稀有なビジネスモデルを持つ企業が多数存在しているのは、この国の市場の特徴だと考える。
「加えて各社の情報発信が充実しており、決算説明会の動画や書き起こしを掲載する企業もあります。その結果、詳細な企業比較がしやすく、たとえば2つの企業において、一人あたりの売り上げの差やその要因について、情報をもとに調べていけることもあるでしょう」
もはや転職先を考える人にとっても「各社のIR情報は参考になるはず」と口にする。それほど充実した内容が多く、日本市場の魅力になっているという。
自身のキャリアを積む場所として、投資の世界を選択した松本氏。その理由について、「小さい頃からわくわくするようなサクセスストーリーを見るのが好きだったからです」と、柔らかい表情で語る。
たくさんの人が関わり、それぞれの意思や熱量が積み重なって企業が成長していく。その過程を見続けたいという思いが、この仕事に就いた一因となった。「個人のサクセスストーリーも素晴らしいものですが、企業のそれは運に左右されることが少なく、私はそちらを追いかけたいと思ったんです」。
未上場の段階から投資するのは、まさにそのストーリーを追いかけることにもつながる。小さな企業がいずれ世界中で使われるサービスを生む。あるいは圧倒的な生産性で成長していく。そんな道のりをファンドマネージャーとして支援しつつ、同じように投資を通じて日本企業にエールを送る人たちが増える未来を望んでいる。
(取材・文/有井太郎 撮影/森カズシゲ)
※記事の内容は2024年12月現在の情報です