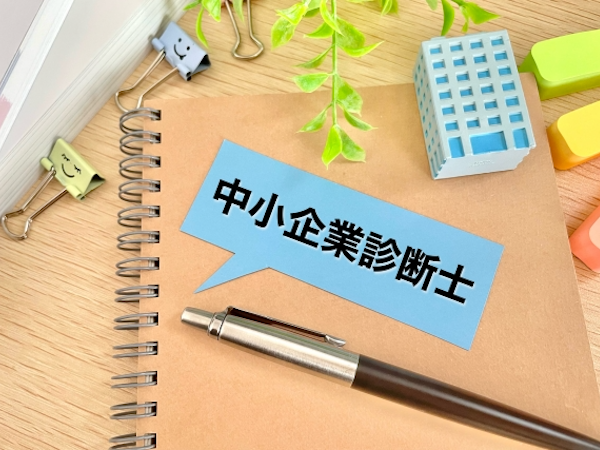中小企業診断士とは?試験概要や資格を取得するメリットを解説
- TAGS.
近年、「リスキリング」という言葉が注目を集めています。変化の早いビジネス環境に対応するため、新しいスキルを学び、自らのキャリアを柔軟に対応させることが求められています。その中で、「資格取得」は、自分自身の専門性を高め、将来の選択肢を広げる有力な手段の一つです。そこで本記事では、中小企業診断士の資格について解説していきます。
中小企業診断士は、中小企業に対してコンサルティングを実施する専門家です。資格を取得するためには、1次・2次試験に合格したうえで、実務補習などを受けなければなりません。
本記事では、中小企業診断士の試験概要や、資格の魅力について解説します。
中小企業診断士とは
中小企業診断士とは、中小企業が抱える経営課題に対応できるように、診断や助言をする専門家のことです。経済産業省は、経営診断や助言について一定の能力を有すると認められる人を「中小企業診断士」として登録しています。
なお、中小企業施策の適切な活用を支援したり、企業と行政や金融機関などのパイプ役として活躍したりするため、中小企業診断士は幅広い知識やスキルが必要です。
中小企業診断士の仕事内容
中小企業支援法によると、中小企業診断士の業務は、中小企業の経営資源に関して適切な経営の診断をしたり、経営に関する助言をしたりすることです。具体的には、以下の業務が挙げられます。
・依頼者の希望に基づき、診断方針を策定する
・依頼者の財務諸表などをチェックする
・経営内容や問題点を依頼者にヒアリングする
・経営上の問題点を分析する
・改善案を報告書にまとめ、具体的な改善策を提案する
上記に限らず、自身の知識やスキルを活用して幅広い分野で活躍する機会があります。
中小企業診断士になる流れ
中小企業診断士になるまでの流れは、以下の通りです。
1. 1次試験(マークシート式)に合格する
2. 2次試験(筆記試験・口述試験)に合格する
3. 実務補習を受ける・実務に従事する
4. 中小企業診断士として登録する
それぞれ解説します。
1次試験(マークシート式)に合格する
中小企業診断士になるには、まずマークシート式による1次試験(7科目)を受験し、合格しなければなりません。ただし、ほかの国家試験に合格していたり、前年・前々年に一部の科目に合格していたりする場合は、対象の試験科目を免除できることがあります。
試験科目は、以下の通りです。
・経済学・経済政策
・財務・会計
・企業経営理論
・運営管理(オペレーション・マネジメント)
・経営法務
・経営情報システム
・中小企業経営・中小企業政策
一般的に、上記の総点数が60%以上で、1科目でも満点の40%未満がない場合に第1次試験の合格者とみなされます。
2次試験(筆記試験・口述試験)に合格する
1次試験に合格したら、2次試験を受験します。まず、短答式や論文式による筆記試験に合格しなければなりません。
筆記試験では、実務の事例問題が4つ出題されます。1次試験と同様に、筆記試験の総点数が60%以上で、1科目でも満点の40%未満がないことが原則として合格の基準です。
筆記試験に合格したら、口述試験を受験します。口述試験の内容は、面接で中小企業の診断・助言に関する能力を問うものです。口述試験における評定が60%以上であることが、合格の基準として設定されています。
実務補習を受ける・実務に従事する
2次試験(筆記試験・口述試験)に合格したら、15日以上の実務補習を受けます。実務補習は、日本中小企業診断士協会連合会で受講可能です。
また、実務補習を受ける代わりに実務に15日以上従事するか、実務補習と実務に従事した日数が15日以上になる場合でも、登録のための要件を満たします。「実務に従事」とは、要件を満たす企業において、中小企業者に対する経営診断・助言業務や、経営の窓口相談業務を遂行することです。
なお、いずれの方法でも、2次試験合格から3年以内に必要日数に達しなければなりません。
中小企業診断士として登録する
15日以上の実務補習を受けるか、実務に従事し終えたら、中小企業診断士として登録する手続きを進めます。手続きには、以下の書類が必要です。
・中小企業診断士登録申請書
・中小企業診断士第2次試験合格証明書
・実務補習修了証書もしくは、実務従事の実績証明書
・住民票の写し
書類を申請し、的確であることが確認され次第、中小企業診断士として登録されます。
なお、中小企業診断士として登録してからも、5年ごとに更新登録の申請が必要です。更新登録の申請をするまでに、専門知識補充要件と実務要件の両方を満たさなければなりません。
中小企業診断士の資格を取得するメリット・魅力
中小企業診断士の資格を取得することのメリット・魅力は主に以下の通りです。
・就職・転職・独立に役立つ
・経営判断やマネジメントの知識が身につく
・ネットワークが広がる
それぞれ解説します。
就職・転職・独立に役立つ
就職や転職に役立つことが、中小企業診断士の資格を取得するメリットです。試験に合格するには財務・IT・人事などさまざまな領域について学ばなければならないため、資格を保有していることを伝えることで、幅広い分野についての知識を身につけていることをアピールできます。
また、独立につなげられる点も魅力です。中小企業診断士の資格を取得したことをきっかけに、コンサルタントとして独立するプランを立てられるでしょう。
経営判断やマネジメントの知識が身につく
中小企業診断士の試験勉強を通じて、経営判断・マネジメント・マーケティングなどの知識が身につくことも魅力です。
経営に関するさまざまな知識を身につけておけば、依頼者が抱える経営課題だけでなく、自社の経営課題の解決策も導き出せるようになります。そのため、転職しなくても現在勤めている会社の経営企画部門やマーケティング部門などで、中小企業診断士としての知識を役立てられるでしょう。
また、将来管理職や経営職につく際にも、中小企業診断士になる過程で得た知識や経験が強みになります。
ネットワークが広がる
ネットワークが広がり、今まで以上に幅広いジャンルの人たちと意見交換できるようになることも、中小企業診断士の資格を取得するメリットです。
中小企業診断士になると、依頼者である中小企業の経営者との接点が増えます。また、仕事を進めるなかで、公認会計士や税理士などの資格を保有している人と交流する機会もあるでしょう。
さらに、勉強会に参加したり、コミュニティに加わったりすることで、中小企業診断士同士の交流も期待できます。
中小企業診断士の試験概要
中小企業診断士の試験には、受験資格が設けられていません。そのため、年齢・性別・学歴などによらず、誰でも受験できます。
1次試験の時期は、毎年8月です。60分・60分・90分・90分と、60分・60分・90分の2日間にわたって試験が実施されます。
2次試験(筆記式)の時期は、毎年10月です。1日で各80分の事例が、合計4問出題されます。
2次試験(口述式)の時期は、毎年1月です。筆記試験の事例に基づき、約10分間の個人面接が行われます。
中小企業診断士の資格を取得するコツ
中小企業診断士の資格取得を目指す場合には、以下を意識しましょう。
・科目ごとに学習時間の配分を変える
・3年計画も検討する
コツをそれぞれ解説します。
科目ごとに学習時間の配分を変える
中小企業診断士の資格を取得するコツのひとつとして、科目ごとに学習時間の配分を変えることが挙げられます。
中小企業診断士の試験は、1次試験だけでも7科目あり出題範囲が広いです。まずは過去問を解いて出題傾向を掴み、苦手な分野に集中するとよいでしょう。ただし、総点数が60%以上で、1科目でも満点の40%未満がないことが合格の基準であることを意識しておくことも大切です。
さらに、試験合格までの時間が限られている場合には、2次試験との関連が深い分野に集中する方法もあります。
3年計画も検討する
仕事との両立が難しく、十分な学習時間を確保できない場合は、3年計画も検討しましょう。
中小企業診断士の1次試験で一部の科目に合格した場合、翌年度と翌々年度の1次試験を受験する際に対象科目を免除できます。そのため、1年目・2年目・3年目と学習する科目を分けておけば、少ない科目を集中的に学べるでしょう。
なお、1次試験の7科目すべてに合格した場合は2年間有効です。つまり、ある年の2次試験に落ちても、翌年に限り1次試験を受けずに再度2次試験に挑戦できます。
中小企業診断士は経営に関する知識が必要な資格
中小企業診断士とは、中小企業に診断や助言をする専門家を指します。中小企業診断士になるためには、1次・2次試験に合格し、実務補習を受けるか実務に従事したうえで、中小企業診断士としての登録が必要です。
また、試験に合格するためには、経営に関する幅広い知識が求められます。その分、管理職や経営職についた際に、得た知識を役立てられる点が魅力です。就職・転職時にアピールでき、独立開業にもつなげやすいため、気になる方はこの機会に学習を始めてみてはいかがでしょうか。
参考:中小企業庁「中小企業診断士とは」
参考:経済産業省「中小企業診断士」
参考:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会「どうしたら中小企業診断士になれるの?」
参考:一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会「令和6年度中小企業診断士第1次試験の試験合格者について」
ライター:Editor HB
監修者:高橋 尚
監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。