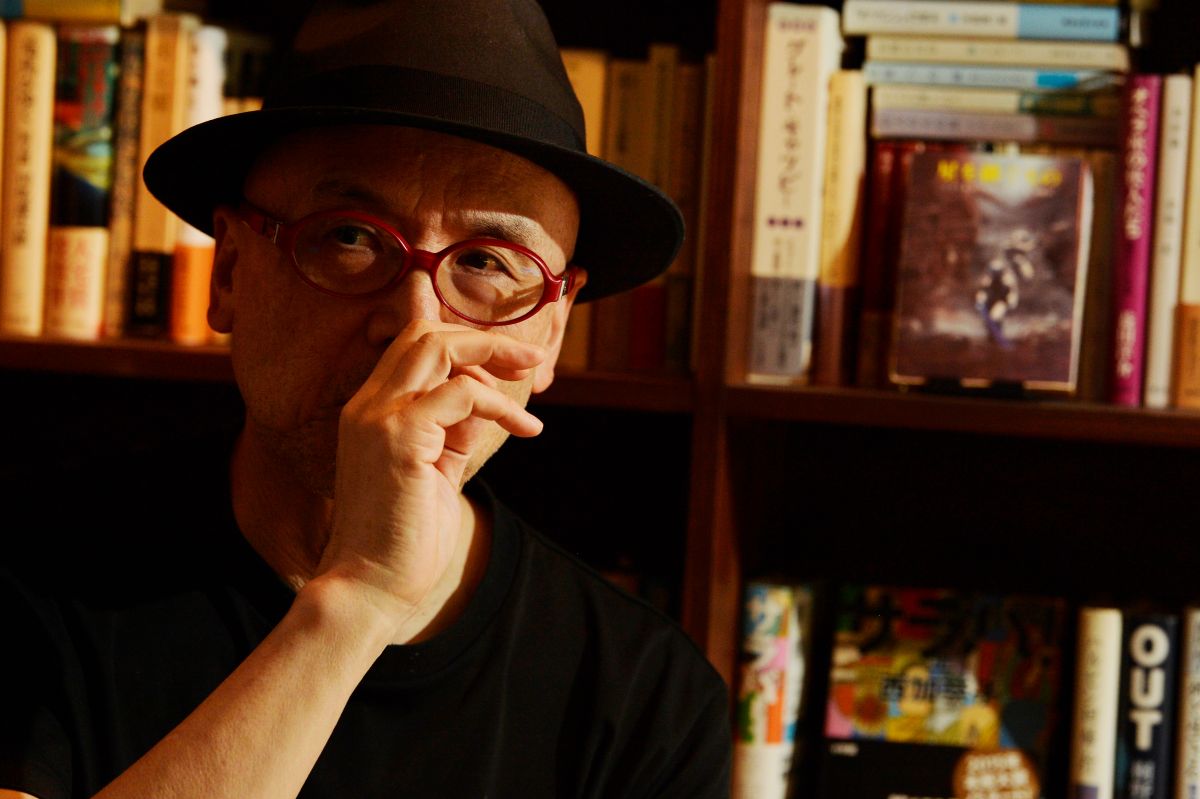企業にも投資家にも重要な考え方「ファンベース」 -後編-
「ファンに愛される企業」ってどんな取り組みをしているの?
- TAGS.
「ファンをもてなす」のではなく「ファンを仲間にする」
三菱地所のような「ファンとの共創」も、ファンベースがあってこそ成立するもの。ただし、「ファンと一緒に新製品を立ち上げる」という意味ではないという。
「ファンがずば抜けたアイデアマンというわけではないので、発案してもらうということではありません。ファンが評価している部分、愛してくれている部分を開発者が知ることで、ファンが求めている商品やサービスが生まれやすくなるということです。ファンの思いを大切にした開発を行うことによって、ファンの熱がさらに高まり、ファン度も上がっていくといえます」
自動車メーカーのマツダは「会いに行ける開発者」として自動車開発主任とファンが交流する機会を設けている。これが新たな開発の種となっているのだ。また、新車を発表する際は、プレス向けの発表会より先にファンに情報を発信するそう。ファンを大切にし、ファンが喜ぶことを実践している。
「マツダがさすがなところは、開発者を表に出しているところです。ファンミーティングやイベントを高級ホテルなどで開催しても、ファンには響かないものです。ファンが本当に喜ぶのは、普段入れない本社のオフィスや会議室に行けたり、社内のスタッフと交流できたりすることだったりします」
また、ファンを接待するのではなく、仲間にすることがポイントとのこと。
「例えば飲食店の場合、『常連客はビール1杯サービス』みたいなことをすると、さらなるサービスを要求してくる悪い顧客になりかねません。では何をすればいいかというと、『最近お店の調子が悪いけど、どうすればいいかな?』と聞いたり、『いま忙しいから、この料理をあのテーブルに届けてもらえる?』とお願いしたりするなど、仲間扱いすることです。そうするとファンは一生懸命応えようとしてくれて、共創へとつながっていきます」
これからの時代のカギとなる「ファンベース」
ファンミーティングでファンと向き合い、ファンが愛してくれている部分を大切にした商品やサービスを生み出す。ファンベースは、ビジネスの基本ともいえる形だ。
「実は当たり前のことで、『本当に好いてくれている人のことを大切にしましょう』という話です。美容院や飲食店などの個店は、お得意様と向き合うファンベースの典型のようなビジネスでしたが、最近はオンラインのクーポンなどを使って新規獲得に走ってしまっています。単発の客に頼ると売上は安定しません。観光業もいまはインバウンド需要で伸びていますが、インバウンドに偏ると国内の常連客が離れかねません。再びコロナ禍のようなことが起きたら、大変なことになるでしょう」
時代が変わっていくとしても、ファンを大切にするというビジネスの基礎は変わらない。その意味を理解している企業は、今後も生き残る可能性が高いという。
「これからAIがさらに進化し、パーソナルエージェントとして個々の嗜好に合わせて買い物をサポートしてくれる世界になっていくでしょう。そうなると広告も口コミも必要なくなるように感じますが、好みに合うものばかり勧められるとセレンディピティ(思いがけない発見)がないように感じてくるはずです。そうなると強いのは、信頼している家族や友人の言葉。AIが勧めるものとは別に、家族や友人が勧めるものの存在感が増してくるはずです。前編で話したように、今後ますますファンの存在が重要になるでしょう」
最後にもうひとつ、これからの社会を生き残る可能性が高い企業の共通点も聞いた。それは「従業員が自身の勤めている企業のファンであること」。
「『うちの会社は真面目にいいことやってるんだよ』と胸を張って言っている人がいたら、いい会社なんだなと思いますよね。それが家族や友人であれば、なおさらそう感じるでしょう。従業員が勤務先のファンになっていると、その思いが周囲に広がり、共感を伴ってファンが増えていくという現象が起こります。顧客だけでなく従業員もファンにしていくことが、今後の企業には求められることかもしれません」
これからのビジネスの基礎となるであろう「ファンベース」。労働者としても消費者や投資家としても、頭の片隅に入れておくと、企業の見え方が変わってくるだろう。
(取材・文/有竹亮介 撮影/森カズシゲ)