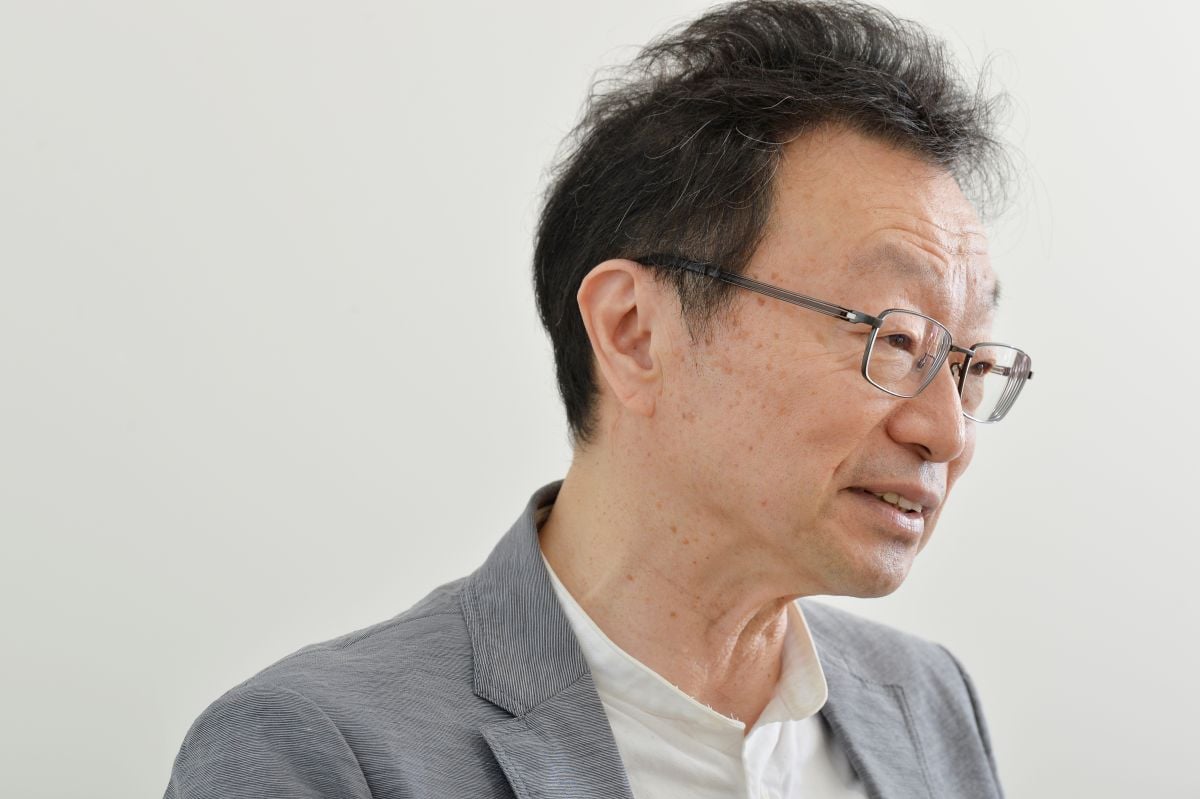人間の生活に不可欠なインフラ「社会的共通資本」前編
東大教授が解説! 現代の日本で「社会的共通資本」が求められる理由
「SDGs」がきっかけで変わり始めている社会
日本でも、先進国を中心とする経済学の流れが浸透し、GDPを上げることが目標となった。そのなかでも、宇沢氏は「社会的共通資本」の大切さを訴えていたという。
「当時、日本の高度成長のためには自動車産業が非常に重要でした。しかし、自動車は排ガスや騒音によって公害を招きますし、道路を占有すると道路を遊び場としていた子どもたちのリスクやストレスが高まります。このような点から、自動車産業は経済的価値が高い一方、社会的価値や環境的価値を損なう可能性があるため、社会的費用の高い産業だと宇沢先生は訴えていました。当時の経済学では、異端の考え方といえます」
2015年に「SDGs」が採択されたことで、ようやく市場は責任を持って社会にかかわっていくべきではないかという方向性に変わっていった。
「近年は、企業の経営戦略が変わり始めています。例えば、ビールを製造するメーカーが非営利的な教育文化活動の支援を行うとともに、工業用水の処理などのメインとなる営利事業に直接付随する社会的責任活動をとても重視しています。社会的責任を経営の軸に据え、企業のカルチャーとして社会貢献を推し進めるところが増えてきています。同時に、『社会的責任を果たしている会社だから投資する』という発想の投資家も出てきています。いわゆるESG投資ですね」
社会が変化のときを迎えているいま、立ち往生している企業も出てきているとのこと。
「『社会的責任の重要性はわかるけど、何をしたらいいのだろう…』と悩んでいる企業は、相当数あると考えられます。そこを解消するためには、ESG評価やKPIの設定といった数値的な指標も大切ですが、そこだけに終始すると達成度だけが重視されてしまいます。ただ数字を追うのではなく、企業のみんなで対話をして社内の気運を高め、従業員にとって見通しがよく、消費者や投資家に対しても説明責任を果たせる組織を目指すことが第一歩ではないかと思います」
現代の日本の課題は「制度疲労」の解消
「日本で『社会的共通資本』の考え方を浸透させるためには、ひとつのハードルがある」と、松島教授は話す。
「日本における一番の課題は『制度疲労』、つまり制度の劣化や制度に対する不信感です。例えば、医療や教育といった誰でも平等にアクセスできるはずの制度が、受益者負担の名のもとに個人責任へと転化され、選ばれた人しか利用できないものになりつつあります。路線バスの廃止や病院の統廃合も、その一例です」
なぜ、現在のような状況になってしまったのか。その背景には、日本の制度運用の見えづらさがあるという。
「公的制度にしても会社の事業にしても、日本は『誰が決めたのか』『なぜそのような内容になったのか』といったことがわかりづらいと感じます。過程が見えないと制度に対する不信感が生まれ、市民や利用者の『無関心』『忖度』を引き起こします。その結果、制度の見直しなどが行われないため、劣化してしまうのです」
マイナンバー制度は、ひとつの事例といえるかもしれない。高機能な技術が用いられた効率的な制度のはずだが、設けられた経緯や制度内容がうまく周知されていないため、信頼や合意形成が十分ではないといえる。
「不安や不信感があったとしても、それを伝える窓口が明確でないことも課題のひとつです。北欧諸国やスイスでは、市民が制度設計の段階から携わる文化が強いため、制度に対する愛着が形成されやすく、『制度は自分たちで育てるもの』と捉えられています。そのため、社会にマッチするように制度も変化しやすいのです。日本も北欧のような方向に踏み出すときだといえるでしょう」
約50年の時を経て、注目されている「社会的共通資本」。生活に欠かせないものであり、誰もが当事者として考えるべきものだといえるだろう。後編では、より具体的な課題解決策について、松島教授に伺う。
(取材・文/有竹亮介 撮影/森カズシゲ)