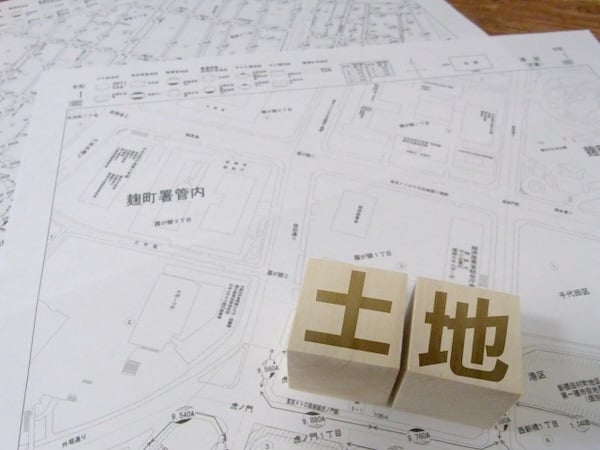路線価とは?調べ方・見方のポイントや土地評価額の計算方法も解説
路線価とは、道路に面している標準的な宅地の1平方メートルあたりの価格を示した指標を指します。相続税路線価と固定資産税路線価で使用目的が異なるため、注意しましょう。
また、路線価は、税金の計算だけでなく、不動産取引や住宅ローンの担保評価にも使われています。仕組みや調べ方を理解しておくと、ビジネスでもプライベートでも役に立つでしょう。
本記事では、路線価とは何か説明した上で、調べ方や見方のポイントについても詳しく解説します。路線価を使って土地の評価格を計算する方法も紹介しているので、参考にしてください。
路線価とは
路線価とは、道路に面している標準的な宅地における、1平方メートルあたりの価格を示したものです。
路線価が記載された地図(路線価図)には、価格が千円単位で表示されています。例えば、路線価図に「150」と記載されている場合、その場所の路線価は1平方メートルあたり15万円です。
なお、路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」があります。この記事で「路線価」として紹介しているのは、基本的に相続税路線価のことです。
路線価の利用方法
相続税路線価と固定資産税路線価では、利用方法が異なります。相続税路線価の利用方法は、相続税・贈与税の評価額を計算することで、固定資産税路線価の利用方法は、固定資産税などの評価額を計算することです。
相続税路線価と固定資産税路線価の概要を説明した上で、それぞれの利用方法について詳しく解説します。
相続税・贈与税の評価額を計算する(相続税路線価)
相続税路線価とは、毎年7月1日に国税庁が公表する、1月1日時点における路線価です。主に、相続税や贈与税の評価額を計算する場面で使われます。
相続税の計算に使われる土地の相続税評価額は、対象の土地における相続税路線価に必要な画地調整率(奥行価格補正率など)や地積をかけて求めることが一般的です。基本的に、相続する土地の相続税路線価が高いほど、評価額が上がり税額も高額になります。
なお、相続税路線価を確認できるのは、国税庁Webサイトの「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」などです。
固定資産税などの評価額を計算する(固定資産税路線価)
固定資産税路線価とは、各市町村(東京23区の場合は東京都)が公表する、1月1日時点の路線価を指します。
固定資産税路線価は国税庁ではなく各市町村が主体となる点や、3年に1回の頻度で評価される点が、相続税路線価と異なる点です。ただし、3年間の据え置き期間中でも、地価の下落がある場合に下落修正の処理がされることはあります。
固定資産税路線価を利用するのは、固定資産税などの税金を計算する場面です。一般的に、固定資産税を計算で使われる土地の固定資産税評価額は、固定資産税路線価に宅地の状況を踏まえて求められます。
固定資産税路線価を確認できるのは、各自治体の固定資産税課などです。東京23区の場合は、東京都のWebサイトで路線価を公開しています。
路線価と公示地価(公示価格)の関係
路線価は、公示地価(公示価格)との関係が深い指標です。公示地価とは、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年3月に公示する、土地(標準地)の1平方メートルあたりの価格を指します。
公表の主体(国税庁か国土交通省か)や公表時期(毎年7月か3月か)などが、路線価と公示地価で異なる点です。いずれも、1月1日時点の価格(価額)である点は共通しています。
また、路線価を決めるにあたっては、不動産鑑定士の評価だけでなく売買事例や公示地価なども参考にしている点がポイントです。そのため、路線価は公示地価の約8割程度を目安として定められています(固定資産税路線価の場合は、公示地価の約7割程度が目安)。
公示地価について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
公示地価(公示価格)とは?基準地価との違いもわかりやすく解説
路線価を調べる流れ
路線価を調べる際は、まず国税庁のWebサイト「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」にアクセスしましょう。次に、「令和7年分財産評価基準を見る」(2025年に調べる場合)で調べたい土地が所在する都道府県の地図をクリックします。
続いて、「財産評価基準書目次」が表示されたら、「路線価図」をクリックしましょう。同じ要領で、市区町村をクリックしたら地名と一緒に路線価図ページ番号が表示されます。
最後に、路線価図ページ番号をクリックして路線価図を表示し、対象の土地の数字(路線価)を確認しましょう。
参考:国税庁「財産評価基準書路線価図・評価倍率表 令和7年分財産評価基準を見る」
路線価図の見方のポイント
路線価図の見方のポイントは、主に以下の通りです。
・記号の意味を理解する
・借地権割合を確認する
・路線価がない場合は評価倍率表を確認する
それぞれ解説します。
記号の意味を理解する
路線価図を正しく読むには、記号の意味を理解しておかなければならないことがあります。
例えば、路線価の数字が丸で囲まれている地域は、「普通商業・併用住宅地区」です。それに対し、無印の地域は「普通住宅地区」であることを意味します。
記号の意味は、各路線価図の上部で確認できるため、必要に応じて都度参照しましょう。
借地権割合を確認する
調査する土地に借地権割合が記されていないかも、確認しておきましょう。
借地権とは、借主が土地を使用できる権利です。借地権割合は、借主が何割程度借地権を有するかを数字で示しています。
路線価の数字の横に振られているA〜Gのアルファベットが、借地権割合を示したものです。例えば、Cが振られていれば、借地権割合が70%であることを意味します。
借地権の評価額の計算式は、以下の通りです。
・借地権の評価額(円) = 土地の評価額 × 借地権割合
そのため、借地権割合が高いほど評価額も高くなります。
路線価がない場合は評価倍率表を確認する
調べたい土地に路線価が設定されていない場合は、固定資産税評価額を市役所・区役所や町村役場などで確認のうえ、国税庁のWebサイトである「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」で評価倍率表を調べて、倍率方式で評価額を計算しなければなりません。
対象の土地の固定資産税評価額に評価倍率表の倍率をかけることで、評価額を計算できます。例えば、宅地の固定資産税評価額が「1,100万円」で倍率が「1.2」であれば、評価額は「1,320万円」です(1,100万円 × 1.2)。
税金の計算以外で路線価が使われる場面
税金の計算以外にも、路線価を活用できる場面はあります。
例えば、住宅ローンの審査で対象物件の担保評価をする際に、路線価が使われることがあります。そのため、購入予定の物件や保有している物件の所在する場所の路線価が高いほど、担保評価額も高くなることが一般的です。
また、路線価を使って計算した価格で、土地の売買価格を推測できることもあります。ただし、実際の売買額は買い手と売り手の需要と供給に基づくため、路線価で計算した額と乖離する可能性もある点に注意が必要です。
路線価を使って土地の評価額を計算する方法
路線価を使って土地の評価額を計算する方法は、その土地の状況によって異なります。「ひとつの道路に面しているケース」「正面(※)と側方に道路があるケース」「正面と裏面に道路があるケース」に分けて、計算方法を押さえておきましょう。
なお、今回借地権割合は考慮していません。
※路線価に奥行価格補正率をかけた際に、高い方の路線
ひとつの道路に面しているケース
ひとつの道路にのみ面している土地の評価額を計算する際の式は、以下の通りです。
・評価額(円) =路線価 × 奥行価格補正率 × 地積
例えば、路線価「120」奥行距離「30メートル」地積「500平方メートル」(普通住宅地区)の場合、評価額は「5,700万円」です(12万円 × 0.95 × 500平方メートル)。
奥行価格補正率は、国税庁の奥行価格補正率表を使って確認できます。普通住宅地区で奥行距離30メートルの場合は、「0.95」です。
正面と側方に道路があるケース
正面と側方に道路がある土地の評価額を計算する際の流れは、以下の通りです。
1. 「正面路線価 × 奥行価格補正率」を計算する
2. 「側方路線価 × 奥行価格補正率 × 側方路線影響加算率」を計算する
3. 1と2を足して、地積をかける
例えば、正面路線価「120」側方路線価「100」奥行距離「20メートル」地積「200平方メートル」(普通住宅地区・角地)の場合、評価額は「2,460万円」です[(12万円 × 1)+(10万円 × 1 × 0.03) × 200平方メートル)]。
側方路線影響加算率は、国税庁の側方路線影響加算率表で確認できます。普通住宅地区で角地の場合は、「0.03」です。
正面と裏面に道路があるケース
正面と裏面に道路がある土地の評価額を計算する際の流れは、以下の通りです。
1. 「正面路線価 × 奥行価格補正率」を計算する
2. 「裏面路線価 × 奥行価格補正率 × 二方路線影響加算率」を計算する
3. 1と2を足して、地積をかける
例えば、正面路線価「120」裏面路線価「80」奥行距離「20メートル」地積「200平方メートル」(普通住宅地区)の場合、評価額は「2,432万円」です[(12万円 × 1)+(8万円 × 1 × 0.02) × 200平方メートル)]。
二方路線影響加算率は、国税庁の二方路線影響加算率表で確認できます。普通住宅地区の場合は、「0.02」です。
路線価とは土地1平方メートルあたりの評価額
路線価とは、道路に面している標準的な宅地における、1平方メートルあたりの価格を示したものです。路線価には、相続税や贈与税の計算に使われる相続税路線価(国税庁が公表)と、固定資産税の計算に使われる固定資産税路線価(各市町村が公表)があります。
路線価は、税金の計算だけでなく不動産の売買や住宅ローンにおける担保評価などでも使われる重要な指標です。一度、自分の居住する地域やマイホームの購入を検討している土地の路線価を国税庁のWebサイトで確認してみてはいかがでしょうか。
参考:国税庁「財産評価基準書路線価図・評価倍率表 路線価図の説明」
参考:国税庁「令和7年分の路線価等について」
参考:国税庁「No.4606 倍率方式による土地の評価」
参考:国税庁「奥行価格補正率表」
ライター:Editor HB
監修者:鈴木 靖子(ファイナンシャルプランナー、AFP認定者)
監修者の経歴:
銀行の財務企画や金融機関向けサービスに10年以上従事。企業のお金に関する業務に携わる中、その経験を人々の生活に活かすためにFP資格を取得。現在は金融商品を売らない独立系FPとして執筆や相談業務を中心に活動中。フリーランスがお金の知識を持つことの大切さを実感しており、フリーランス向けマネーブログを運営している。