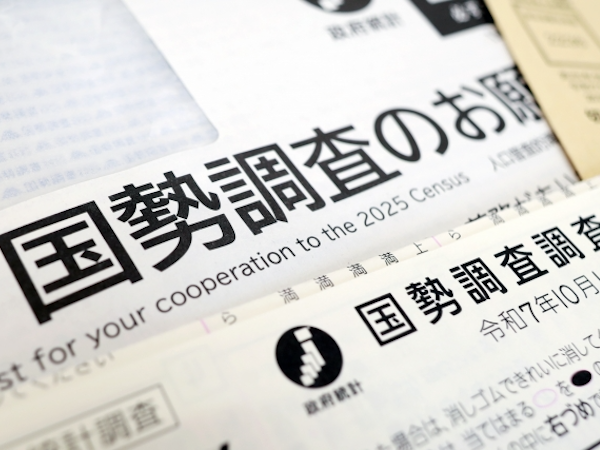国勢調査とは?目的・回答の流れ・活用事例をわかりやすく解説
- TAGS.
国勢調査とは、5年に一度日本に住むすべての人や世帯を対象として実施する重要な統計調査です。2025年10月1日には、第22回調査が実施されました。
全数調査のため、標本調査よりも正確な数字を把握できる点が国勢調査の特徴です。自分や自分の世帯について回答する、調査結果をビジネスに活用するなどで関わる機会の多い調査のため、仕組みや内容を理解しておきましょう。
本記事では、国勢調査とは何かを説明したうえで、調査項目や活用事例についてもわかりやすく解説します。
国勢調査とは
国勢調査とは、国内の人や世帯の実態を把握することを目的にした調査のことです。日本に住むすべての人や世帯を対象にしており、日本で最も重要な統計調査とされています。
ここで、国勢調査の実施時期や実施方法について押さえておきましょう。
調査時期
国勢調査は、5年に一度実施される調査です。1920年から調査が始まり、2025年10月1日には第22回調査が実施されました。
唯一「5年に一度」の周期にしたがって実施されなかったのが、第6回です。本来は1945年が第6回の調査年でしたが、緊迫する戦時下の状況により中止されたため、代わりに1947年に臨時で調査を実施しています。
調査方法
国勢調査は、全数調査により実施されます。全数調査とは、対象となるものをすべて調査する方法のことです。
全数調査には、膨大な費用や手間がかかります。それにもかかわらず国勢調査が全数調査による理由は、正確で信頼できる方法で調査が求められるためです。全数調査の代わりに標本調査(※)を用いると標本誤差が含まれるため、産業や職業を細かく分類するなかで誤差が大きくなる可能性があります。
※標本調査:対象となるものの一部を調査して全体を推定する方法
国勢調査の調査項目
国勢調査の調査項目は、「世帯員に関する事項」と「世帯に関する事項」に分類できます。2025年の国勢調査における調査項目は、それぞれ以下の通りです。
【世帯員に関する事項】
・氏名
・男女の別
・出生の年月
・世帯主との続き柄
・配偶の関係
・国籍
・現在の住居における居住期間
・5年前の住居の所在地
・就業状態
・所属の事業所の名称及び事業の種類
・仕事の種類
・従業上の地位
・従業地又は通学地
【世帯に関する事項】
・世帯の種類
・世帯員の数
・住居の種類
・住宅の建て方
なお、調査項目は行政上の必要性や諸外国との比較可能性、回答にかかる負担などを考慮したうえで決められています。そのため、次回は調査項目が変わる可能性もあるでしょう。
国勢調査への回答は義務?
法律(統計法第13条)で、調査対象となる世帯の世帯主や世帯員に対して、調査票に記載されている事項について報告することを義務付けています。日本に住んでいれば基本的に対象になるため、必ず回答しましょう。
なお、国勢調査における回答内容は保護されています。統計調査に従事する人には守秘義務や罰則が設けられており、統計外の目的に使用することや、外部に持ち出されることはありません。
国勢調査の回答から集計までの流れ
国勢調査の回答から集計までの流れは、以下の通りです(かっこ内は2025年の実施時期)。
1. 書類が各世帯に配布される(9月下旬〜)
2. インターネットや調査票で回答する(〜10月8日)
3. 調査票が総務省統計局に集められる
それぞれ解説します。
1. 書類が各世帯に配布される
9月下旬ごろから、統計調査員が調査票を対象となる各世帯に配布し、記入と提出を依頼します。
統計調査員は、任命期間中一時的に公務員の身分をもつ非常勤の国家公務員もしくは地方公務員です(※)。各家庭を訪問する際に、調査員証や調査専用の手さげ袋を身につけています。
※一部の地域では、調査員事務を受託した事業者が調査を実施
2. インターネットや調査票で回答する
調査対象者は、自宅に書類が届いたらインターネットで回答するか、調査票に記入して統計調査員に提出します。インターネットで対応すれば、その場で回答・提出を終えられるため便利です。
期日(2025年:10月8日)までにインターネットや調査票での対応が済んでいない場合には、調査員からあらためて回答の依頼をされます。2025年のケースでは、調査員が提出のお願いで各家庭を訪問する期間は、10月17日〜10月27日でした。
3. 調査票が総務省統計局に集められる
提出した調査票は、市区町村や都道府県を経由して総務省統計局に集められます。また、実際に集計作業を実施するのは、独立行政法人 統計センターです。
なお、総務省の資料「令和2年国勢調査実施状況(実査編)」によると、2020年における調査票の回収率は80.2%(暫定値)でした。近年、報告義務があるにもかかわらず回収率が低下していることが課題です。
国勢調査結果の活用事例
国勢調査結果の主な活用事例は、以下の通りです。
・選挙や都市計画策定などの「人口」の基準にする
・国・地方公共団体の行政に利用する
・民間企業が消費者ニーズを理解するために利用する
・公的統計を作成するための基準にする
それぞれ解説します。
選挙や都市計画策定などの「人口」の基準にする
国勢調査の結果は、各種法令に基づき「人口」の基準として利用されています。
衆議院の小選挙区の改定が、国勢調査の結果を「人口」の基準とした具体例です(衆議院議員選挙区画定審議会設置法)。2020年の国勢調査結果による各都道府県の人口に基づき定数配分を行ったことで、2022年12月28日より5都県で定数が1〜5増加、10県で定数が1減少しています。
そのほか、地方自治法で用いる人口や(地方自治法)、地方交付税の算定への利用(地方交付税法)も具体例です。
国・地方公共団体の行政に利用する
国や地方公共団体の行政にも、国勢調査の結果が利用されています。
例えば、より現状に即した子育て支援のための施策や高齢者福祉政策を立てるには、世帯構成などを正しく把握しておかなければなりません。そこで、国勢調査による男女・年齢別人口や高齢者のいる世帯などの結果が活用されています。
また、災害時の避難所などを作るためにはより正確なデータが求められるため、防災関連でも、国勢調査の結果が重要です。
民間企業が消費者ニーズを理解するために利用する
消費者ニーズを理解する目的などで、民間企業でも国勢調査の結果を活用することがあります。
特定の地域にどのような層が居住しているか把握することで、商品やサービスの需要予測が可能です。関連して、企業の出店計画を立てるのにも役立つでしょう。
企業だけでなく、経済学や社会学など大学の学術研究にも国勢調査の結果が使われています。
公的統計を作成するための基準にする
国勢調査の結果は、将来人口推計を始めとする、公的統計を作成するための基準となることもあります。
将来人口推計とは、過去のデータを投影することで、将来の人口規模や年齢構成などの推移を推定することです。特に、出発点となる人口を算出する際に、国勢調査の結果が使われています。
そのほか、世帯を対象とする統計調査の標本設計なども、調査結果が使われているケースです。
国勢調査の結果を確認する方法
これまでの国勢調査の結果は、政府統計の総合窓口(e-Stat)で確認できます。e-Statのサイトにアクセスして、キーワード検索に「国勢調査」と入力してみましょう。
画面が遷移したら、「国勢調査」の行で「詳細」をクリックします。その後、「国勢調査の統計データはこちらからご参照ください」をクリックしましょう。
第1回の調査結果から直近の結果、時系列データなどが、ファイルもしくはデータベースで確認できます。例えば、データベースで「時系列データ」を選択して「世帯」「世帯の種類別世帯数及び世帯人員」をクリックしていけば、100年前のデータとの比較も可能です。
1920年の1世帯当たり人員は約4.89人であったのに対し、2020年の1世帯あたり人員は約2.23人でした。このように、国勢調査の結果を確認すると、世帯構成に大きな変動が生じていることがあらためてわかります。
参考:e-Stat「統計データを探す」
国勢調査は5年に一度全世帯で実施される調査
国勢調査とは、日本に住むすべての人や世帯を対象に、5年に一度実施される調査のことです。法律で回答が義務付けられているため、調査票を受け取ったら必ず対応しましょう。
「人口」の基準としたり、政策を立案する際の指標としたりするなど、国勢調査の結果は様々な場面で活用されています。特定の地域に居住する層を把握することでマーケティングにも役立てられるため、まずはビジネスで関わっているエリアについてe-Statを使って調べてみてはいかがでしょうか。
参考:東京都「国勢調査 国勢調査ってなあに?」
参考:総務省統計局「令和7年国勢調査の概要」
参考:総務省統計局「なるほど統計学園 全数調査・標本調査」
参考:総務省統計局「令和2年国勢調査有識者会議(第8回)資料1 令和2年国勢調査実施状況(実査編)」
ライター:Editor HB
監修者:高橋 尚
監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。