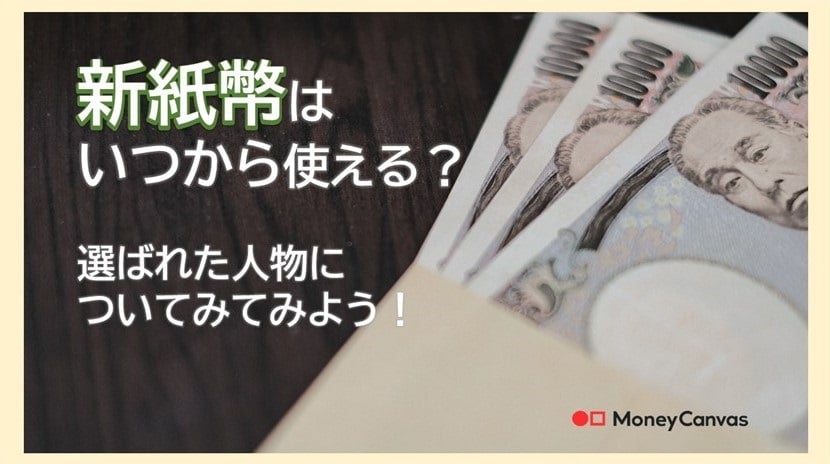新紙幣はいつから使える?選ばれた人物について詳しくみてみよう!
提供元:Money Canvas
- TAGS.
2024年7月3日から、新しい1万円札、5千円札、千円札が発行されます。
1万円札には渋沢栄一、5千円札には津田梅子、千円札には北里柴三郎が描かれます。
現在の紙幣が作られたのは20年前の2004年。中でも1万円札の福沢諭吉は1984年から描かれ、40年ぶりに人物変更となります。「諭吉ファンデ」「諭吉コスメ」のように1万円の代名詞として福沢諭吉に慣れ親しんだ人も多いのではないでしょうか。
紙幣は約20年の周期で作り変えられています。
なぜ紙幣は定期的に変更されるのでしょうか。また選ばれる人物は誰がどのように決めているのでしょうか。
新札に描かれる人物とは?
新札に描かれる人物については、通貨行政を担当する財務省、発行元の日本銀行、製造元の国立印刷局の3者により協議を行い、最終的には日本銀行法に基づき財務大臣が以下のような方針で選定します。*1
1)日本国民が世界に誇れる人物で、教科書に載っているなど、一般によく知られていること。
2)偽造防止の目的から、なるべく精密な人物像の写真や絵画を入手できる人物であること。
現在まで17人が紙幣に登場しており、そのうち女性が描かれたのは明治時代の神宮皇后と現5千円札の樋口一葉の2人です。新紙幣で描かれる津田梅子は2代連続で、3人目の女性ということになります。
新1万円札の渋沢栄一
新しい1万円札には福沢諭吉に代わり、渋沢栄一が描かれます。

渋沢栄一は、天保11年(1840年)に現在の埼玉県深谷市の農家に生まれました。家業である畑作や、当時染料として重要だった「藍玉」の製造・販売、養蚕を手伝う一方で、幼い頃から父親に学問の手ほどきを受けています。従兄弟である尾高惇忠氏からは「論語」などを学びました。*2
その後郷里を離れ、のちに江戸幕府の15代将軍となる一橋慶喜氏に仕えることになります。そして徳川慶喜将軍の実弟、のちの水戸藩主である徳川昭武に随行しパリの万国博覧会を見学するほか欧州諸国の実情を見聞し、先進諸国の社会の内情に広く通ずることができました。
そして明治維新が訪れて以降、大蔵省に在籍、大蔵省を退任したのちに今度は経済人として、日本初となる銀行「国立第一銀行(現在のみずほ銀行)」*3の設立をはじめ、生涯に約500もの企業に関わったほか、約600の教育機関・社会公共事業の支援並びに民間外交に尽力し、「日本の資本主義の父」と呼ばれています*4。
新5千円札の津田梅子
新しい5千円札には樋口一葉に代わり、津田梅子が描かれます。

津田梅子は幕末の1864年に、現在の東京都新宿区にあたる「南御徒町」と呼ばれていたエリアで、藩士の屋敷に生まれました。
当時は女性差別が強く、生まれた子が女の子だと知った父・津田仙は、がっかりして仏頂面で家をとびだしてしまったというエピソードもあります*5。
しかし、父である津田仙は、ペリー来航後に通訳としてアメリカへの使節団に参加し、持ち帰った書籍を4歳だった梅子に見せており、また、梅子のあとに跡取り息子ができたことに安心し、梅子を可愛がるようになりました。
梅子はわずか6歳にして明治4年に欧米視察の岩倉使節団に参加、11年の時を経て帰国します*6。
そこから再渡米などを経て、明治33(1900)年に私立女子高等教育における先駆的機関のひとつ、「女子英学塾」(現在の津田塾大学)を創設し女子の高等教育に尽力しました。女子教育の先駆者であり、歴史的な人物といえるでしょう。
新千円札の北里柴三郎
新しい千円札は野口英世に代わり、北里柴三郎が描かれます。

北里柴三郎は嘉永6(1853)年に現在の熊本県阿蘇郡の庄屋の家で生まれ、その後18歳になってオランダの軍医に師事したことで医学への道を志します*7。
その後、予防医学の重要性を確信し、福沢諭吉氏らの支援のもと、明治25(1892)年に私立伝染病研究所を創立し、後進の育成を行いました。
現在の医療機関「北里研究所」を築いた医学者でペスト菌の発見で知られている人物でもあります*8。
現在の紙幣はいつまで使える?
新紙幣をご紹介してきましたが、現在の「旧」紙幣はいつまで使えるのでしょうか。
日本銀行によれば、一度発行された銀行券は、法律上の特別な措置がとられない限り、この通用力を失うことはありません。つまり、同じ金額が担保されているということです*9。
ただ、あまりにも古すぎる紙幣の場合、使える場所が限られてきます。ATMや自動販売機で使えないということもあるので注意が必要です。
まとめ
ここまで、新紙幣に描かれる人物像についてみてきました。
キャッシュレスが進む現代ですが、いまだ現金への信頼が高い日本。
こうした背景を基に、描かれる人物像について知見を高めてみてはいかがでしょうか。
本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。
出典
*1 「お札の肖像について」国立印刷局
*2「渋沢栄一略歴」渋沢栄一記念財団
*3「日本で最初にできた銀行はどこですか?」日本銀行
*4「日本の資本主義の原点とこれからの新しい時代」独立行政法人経済産業研究所
*5「津田梅子の生き方(1)〜女性は、生まれたときから差別されていた〜 」東京都北区
*6「津田梅子について」津田塾大学
*7、8「北里柴三郎の生涯」北里研究所北里柴三郎記念博物館
*9「お札に関するよくあるご質問」国立印刷局
(Money Canvas)
関連リンク