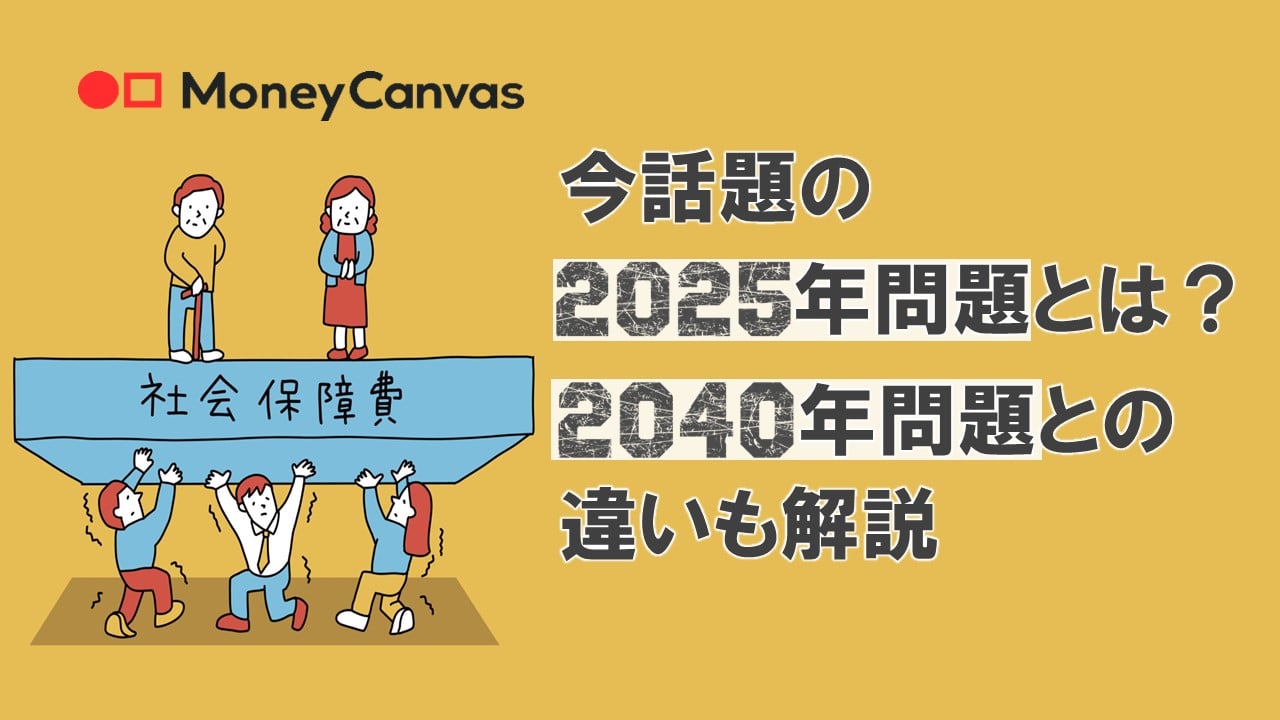今話題の2025年問題とは?2040年問題との違いも解説
提供元:Money Canvas
- TAGS.
「2025年問題」や「2040年問題」という言葉を耳にする機会が増えていますが、具体的に日本社会にどんな変化が起こるのでしょうか。
これらは日本の人口構造の変化に伴い生じる社会問題を指す言葉で、医療・年金・介護といった社会保障制度やインフラの維持、労働力人口の減少など様々な分野への影響が懸念されています。
本記事では、高齢化の節目となる2025年と2040年に焦点を当て、分かりやすく日本社会の課題と今後の備えについて解説します。
2025年問題とは?
2025年問題とは、人口規模の大きい「団塊の世代」(1947~1949年生まれの約800万人)が2025年に全員75歳以上の後期高齢者となり、日本が一気に超高齢社会へ突入することで生じる諸問題を指します。*1
団塊の世代が一斉に後期高齢者入りすることで、日本社会には次のような問題が懸念されています。
社会保障費の増大
高齢者の増加に伴い、年金や医療・介護にかかる社会保障給付費が急増します。
政府試算によれば、団塊世代が後期高齢者となる2025年度には、医療・介護分野の給付費が従来よりも大幅に膨らみ、介護給付費は約1.4倍、医療給付費は約1.3倍に拡大すると見込まれています。*2
社会保障費を支える現役世代の負担も増え、制度の持続性に課題を突き付けています。
医療・介護需要の急増と人材不足
75歳以上では健康状態の悪化により医療や介護サービスのニーズが高まります。
介護現場では既に人材不足が問題となっており、団塊世代全員の後期高齢化によってサービス供給が追いつかなくなる懸念があります。
労働力不足の深刻化
少子高齢化により、生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けています。1995年に約8,716万人いた働き手世代は、2023年時点で約7,395万人まで減少しました。*3
2025年以降、団塊世代の大量引退も加わり、この労働力人口の減少に拍車がかかります。
高齢化社会が進むと働く世代よりも支えられる世代(子ども・高齢者)の方が多くなるため、企業の人手不足や生産力低下が一段と顕著になると指摘されています。
現に2020年時点で高齢者1人を支える現役世代は約2.1人でしたが、2038年には1.7人まで低下すると推計されています。*4
2040年問題とは?
2040年問題とは、1970年代前半生まれの「団塊ジュニア世代」(第二次ベビーブーム世代)が高齢者(65歳以上)となり、日本の高齢者人口がピークを迎える2040年前後に予想される社会問題の総称です。
2040年頃の日本では高齢者人口が過去最大の約35%(総人口の3分の1強)に達すると試算されています。*5
実数で見ると2040年頃には65歳以上人口が約4,000万人、15~64歳の生産年齢人口がおよそ6,000万人と見込まれており、働き手1人で高齢者約0.67人を支える非常に厳しい社会構造になります。*7
この時期には、高齢者の急増と現役世代の急減が同時進行するため、日本の経済活動や社会保障制度維持に深刻な影響が及ぶと指摘されています。
労働力人口の急減と社会保障の持続性
少子化の影響で2040年頃の生産年齢人口は約6,000万人と、2000年頃より2千万人近く減少します。*6
一方で高齢者は約4,000万人とピークに達し続けて医療・年金給付が最大規模になります。現役世代の減少により社会保険料収入は縮小する一方、支えられる高齢者が増えることで年金財政や医療保険財政のバランスが崩れ、制度維持が困難になる恐れがあります。
政府の推計でも、社会保障給付費の対GDP比は2018年度の約20.8%から2025年度に21.6%、2040年度には23.5~23.7%に達すると見込まれており、国家経済に占める社会保障負担の重みが一段と増すことが示されています。*7
医療・介護ニーズのピークと人材・財源不足:
2040年前後は、高齢者人口のピークに伴い医療・介護サービス需要も最大化すると予想されます。
しかし、その需要を支える人材の確保が極めて難しくなる点が問題視されています。
現時点でも介護士や看護師不足が指摘されていますが、2040年には現役世代そのものが少なくなるため、必要な医療・介護人材を十分に確保できない恐れがあります。
財源面でも、社会保障費の増大に対処するためには現役世代の負担増か給付抑制が避けられず、医療の提供体制や介護保険制度の見直しが迫られるでしょう。
インフラ・公共施設の老朽化問題
戦後から高度成長期にかけて集中的に整備された道路や橋梁、上下水道、公共施設などが、2040年前後に次々と築後50年以上となります。
例えば国土交通省の予測では、2040年時点で道路橋の約75%、トンネルの約52%が建設後50年超となる見込みです。*8
老朽インフラの維持・更新には莫大な費用と人員が必要ですが、人口減少で税収や技術者が不足する中、どのように安全を確保していくかが大きな課題です。
インフラ維持を怠れば事故や災害リスクが高まるため、限られた資源で効率よく更新していく戦略が求められています。
地域間格差・地方の過疎化
高齢化の進行速度や人口減少の影響は地域によって異なります。
一般に地方の中小自治体ほど少子高齢化が深刻で、都市部に比べ早い段階で人口減少や高齢者比率のピークを迎える傾向があります。
すでに若年層の流出や出生数減少が著しい地域では、2040年を待たずとも財政難や地域コミュニティの維持困難といった問題が顕在化しつつあります。
2025年問題と2040年問題の違い
2025年問題と2040年問題はいずれも、急速な少子高齢化という人口構造の変化に起因する問題です。
日本社会における高齢者の割合が飛躍的に高まることで、医療・介護の需要増大や年金財政の悪化、働き手の減少といった負担が現役世代にのしかかる点では共通しています。
2025年問題は、団塊の世代が後期高齢者入りすることに伴う短期的・直接的な影響に焦点が当てられています。
医療費・介護費の急増や社会保障財政の圧迫、介護人材不足など、比較的目前の危機として語られることが多く、2020年代後半の日本が直面する「高齢化ショック」とも言える現象です。*2
これに対し2040年問題は、さらにその先の長期的・構造的な課題を含んでいます。
高齢者人口のピークによる社会保障制度の持続困難やインフラ老朽化、地域社会の崩壊リスクなど、日本社会のあらゆる分野にわたる包括的な問題として議論されます。
2040年に向けて行うべき対策
2040年問題までの時間軸を見据え、私たち一人ひとりや社会全体が早めに備えておくことが重要です。
ここでは、超高齢社会を乗り越えるために個人レベルでできる対策をいくつか紹介します。これらは結果的に日本全体の持続可能性にも寄与する大切なポイントです。
生活習慣を整える
まずは健康寿命の延伸を意識しましょう。高齢期になってもできるだけ心身とも健康な状態を保てれば、医療や介護にかかる費用・負担を大幅に減らすことができます。
厚生労働省のデータによると、日本人の平均寿命と健康寿命(健康上問題なく日常生活を送れる期間)との差は男性で約8.7年、女性で約12年あります。
この期間を少しでも縮めることが、高齢化による社会保障費増大を緩和する鍵となります。
具体的には、栄養バランスの良い食事や適度な運動, 定期的な健康診断の受診や持病の管理など、日頃の生活習慣を整えることが重要です。国も「健康日本21」などの施策で国民の健康寿命延伸を目標に掲げています。*9
将来のための貯蓄を行う
少子高齢化が進むほど、公的年金や社会保障だけに頼る生活は難しくなると予想されます。
そこで重要なのが早いうちからの資産形成です。現役世代のうちから計画的に貯蓄や投資を行い、老後に備えた十分な資金を用意しておくことで、高齢期の生活の安心感が大きく違ってきます。
たとえば、NISA(少額投資非課税制度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)といった税制優遇制度を活用するのも賢い方法です。
2024年からは新NISA制度がスタートし、年間投資枠が最大360万円、非課税保有枠も生涯で1,800万円まで大幅に拡充されました。
非課税期間も従来は最長20年でしたが、新NISAでは非課税期間が無期限化され、いつ始めても長期の積立投資が有利に行えるようになっています。*10
これらの制度を活用し、長期・積立・分散投資でコツコツと資産を増やすことが将来への備えになります。また、金融リテラシーを高めておくことも大切です。
預貯金だけでなく債券・株式・投資信託など適切にポートフォリオを組み、インフレや金利変動にも耐えうる資産を持つことで、老後の公的年金に多少の不足があっても自助努力でカバーできる余力をつけておきましょう。
スキルアップし続ける
超高齢社会では「人生100年時代」と言われるように、定年後も長い時間があります。
2040年頃には高齢者も含めた働き方の多様化が進み、希望すれば70歳以上でも働ける社会が一般的になっている可能性があります。
そのため、若いうちからそして定年後も学び直し(リスキリング)やデジタルスキルの習得を続けることが重要です。
現に日本では高齢者の就業率は上昇傾向にあり、2022年には65歳以上人口の約25.2%が何らかの仕事に就いています。*11
人口減少社会をどう乗り越えるか
日本はこれまで経験したことのない人口減少・超高齢化社会に突入しています。
2025年問題・2040年問題は、その中で浮かび上がった大きな節目であり、日本社会の転換点とも言えます。
これらの問題を乗り越えるためには、個人の備えと社会全体の意識変革の両輪が欠かせません。
個人レベルでは、健康寿命を延ばす生活習慣づくりや計画的な資産形成、生涯にわたる学び直しによって、できるだけ「支える側」として充実した人生を送る努力が求められます。
一方、社会レベルでは、高齢者も含め誰もが活躍できる仕組みづくりや、生産性を上げる技術革新、地域コミュニティで支え合う仕組みの強化など、発想の転換が必要でしょう。
若い世代と高齢世代がお互いを支え合い、多様な人材が活躍できる社会へと舵を切ることで、日本は人口減少社会を乗り越えることができるはずです。
「人生100年時代」にふさわしい社会システムとライフプランを追求することこそが、2025年問題や2040年問題を克服し明るい未来を切り拓くカギと言えるでしょう。
本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意ください。
最終的な投資判断、金融商品のご選択に際しては、お客さまご自身の判断でお取り組みをお願いいたします。
出典
*1 ジチタイワークスWEB「5人に1人が後期高齢者に!「2025年問題」で何が起きる?背景や対策を解説」
*2 サライ 「【ビジネスの極意】4人に1人が後期高齢者になる「2025年問題」の影響と対策」
*3 内閣府 「高齢化の状況」
*4 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計) 結果の概要」
*5 ジチタイワークスWEB「2040年問題とは?定義や課題、今後の対策を詳しく解説」
*6 野口悠紀雄 note「20年後の日本と世界を考える:将来人口推計が意味するもの」
*7 厚生労働省「2040年を見据えた社会保障の将来見通し」
*8 国土交通省 「社会資本の老朽化の現状と将来」
*9 一般社団法人 高齢者住宅協会「厚労省:健康寿命(2019)が男性72・68歳、女性75・38歳に」
*10 Money Canvas「【2024年改正】新NISAの全解説: 改正ポイントと注意点で賢く資産運用」
*11 統計局 「高齢者の就業」
(Money Canvas)
関連リンク