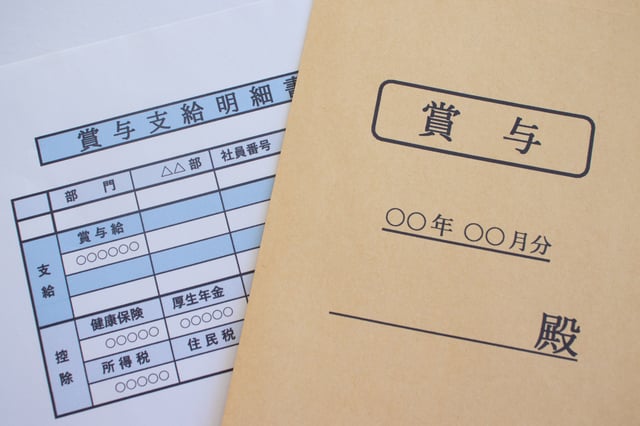毎月の給与額が多い人ほどメリットが大きいらしい
大企業が導入し始めている「賞与の給与化」で社会保険料の負担が減るって本当?
ソニーグループは一部社員を対象に、2025年から冬の賞与(ボーナス)を廃止し、その分を毎月の給与と夏の賞与に振り分けると発表した。月給は最大14%アップするという。「賞与の給与化」と呼ばれる制度変更で、大和ハウス工業やバンダイにも同様の動きが見られている。
大企業はなぜ「賞与の給与化」に踏み出しているのだろうか。会社の狙いと従業員にとってのメリットを、ファイナンシャルプランナーで社会保険労務士の川部紀子さんに教えてもらった。
「賞与の給与化」で社会保険料が下がる可能性大
「会社が『賞与の給与化』に踏み切る理由のひとつに、人手不足の問題があるといえます。賞与を分割して毎月の給与に繰り入れることで、単純に給与額が上がりますよね。当然ながら求人票に記載される給与額も上がるので、求職者の目を引きやすくなります。就職・転職活動を行う際、給与額はしっかりチェックする一方で、賞与額はあまり意識しないという人は多いでしょう。なかには、賞与の不確実性を認識している人もいるため、『賞与の給与化』によって求職者が集まりやすくなり、人手不足が解消する可能性が高くなるのです」(川部さん・以下同)
人手不足は日本企業にとって大きな課題となっているため、年収を変えずに給与額を高く見せることができる「賞与の給与化」は、効率的な人材確保の手段といえるだろう。ただし、会社側の狙いはこれだけではないとのこと。
「特に高収入の従業員の『社会保険料の削減』の目的も考えられます。給与や賞与は、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料)が差し引かれて振り込まれますが、社会保険料には上限があります。給与で多く支払ったほうが上限に達しやすいので、賞与を分割して給与化することで社会保険料を抑えられる可能性が出てきます。社会保険料は労使折半(労働者と事業主が半分ずつ負担すること)となっているため、従業員も会社も負担を軽減することができるのです」
健康保険料・介護保険料は月々の給与が135万5000円以上の場合、どれだけ給与額が上がっても標準報酬月額139万円で計算される。厚生年金保険料はさらに上限が低く、月々の給与が63万5000円以上であれば、標準報酬月額65万円で計算される。
賞与に関しては、給与よりも上限が高い。健康保険料・介護保険料の標準賞与額の上限は年間累計額573万円、厚生年金保険料の上限は1カ月当たり150万円と設定されているため、給与よりも社会保険料が大きくなりやすいといえる。
東京都で働く会社員(45歳、月々の給与100万円、賞与180万円(賞与年2回))を例に、「賞与の給与化」が行われないケースと行われるケースでシミュレーションしてみよう。
●「賞与の給与化」が行われない場合(令和7年度東京支部の保険料率をもとに概算)
給与:100万円(健康保険料・介護保険料の標準報酬月額98万円/厚生年金保険料の標準報酬月額65万円)
賞与:180万円
【給与】
健康保険料・介護保険料:98万円×11.5%÷2=5万6350円
厚生年金保険料:65万円×18.3%÷2=5万9475円
雇用保険料(一般の事業の場合):100万円×0.55%=5500円
【賞与】
健康保険料・介護保険料:180万円×11.5%÷2=10万3500円
厚生年金保険料:150万円×18.3%÷2=13万7250円
雇用保険料(一般の事業の場合):180万円×0.55%=9900円
年間の社会保険料の合計:195万7200円
●「賞与の給与化」が行われた場合(令和7年度東京支部の保険料率をもとに概算)
給与:130万円(健康保険料・介護保険料の標準報酬月額133万円/厚生年金保険料の標準報酬月額65万円)
【給与】
健康保険料・介護保険料:133万円×11.5%÷2=7万6475円
厚生年金保険料:65万円×18.3%÷2=5万9475円
雇用保険料(一般の事業の場合):130万円×0.55%=7150円
年間の社会保険料の合計:171万7200円
「給与と賞与が分かれている場合、別々に社会保険料の計算が行われるため、賞与の分も社会保険料が発生します。しかし、そもそもの給与が上限を超えている人であれば、賞与の分を上乗せしても社会保険料は変わらないだけでなく、賞与で発生するはずだった社会保険料がなくなることになります。そのため、高収入の従業員が多いであろう大企業で『賞与の給与化』が始まったと見る向きもあるでしょう」
「高収入」であることがポイントであり、平均年収くらいだと「社会保険料の削減」の効果はほとんどないとのこと。
「平均年収くらいだと、『賞与の給与化』によって社会保険料が安くなる人もいれば高くなる人もいますし、その違いはわずかだといえます」