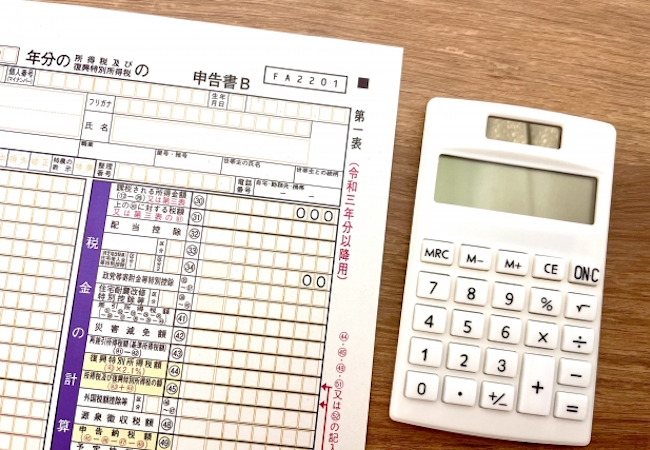給与所得控除とは?他の所得控除との違いや計算方法もわかりやすく解説
給与所得控除とは、給与所得を算定する際に給与収入から引ける金額を指します。確定申告や年末調整の場面で、使うことがあるでしょう。
本記事では、給与所得控除の概要や計算方法に加え、103万円の壁との関係についても解説します。
給与所得控除とは
給与所得控除とは、給与所得を算定するにあたって、給与などの収入金額から引ける金額のことです。給与所得控除額は、対象者の給与などの収入金額によって決まります。
ここから、給与所得控除の対象者や、給与所得控除額の表、自分の給与所得控除額を確認する方法について見ていきましょう。
給与所得控除の対象者
給与所得控除の対象者は、給与所得を得ている人です。給与所得とは、使用人や役員などが受け取る主に以下のような給与に関する所得を指します。
・給料
・俸給
・賃金
・歳費
・賞与
そのため、正社員に限らず、パートやアルバイトなど給与を受け取っている人全員が給与所得控除の対象となります。一方、副業で給与を受け取らず、自身が営む事業のみで生計を立てている個人事業主やフリーランスなどは、給与所得控除の対象外です。
給与所得控除額の表(2020年〜)
給与所得控除の額は、対象年における給与収入額によって決まります。給与収入額と給与所得控除額の関係を示した表が、以下のとおりです(2024年4月1日現在)。
| 給与などの収入金額 | 給与所得控除額 |
| 〜1,625,000円 | 550,000円 |
| 1,625,001円〜1,800,000円 | 収入金額 × 40% − 100,000円 |
| 1,800,001円〜3,600,000円 | 収入金額 × 30% + 80,000円 |
| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入金額 × 20% + 440,000円 |
| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入金額 × 10% + 1,100,000円 |
| 8,500,001円〜 | 1,950,000円 |
例えば、給与収入が700万円の場合、「6,600,001円〜8,500,000円」に該当します。そのため、「700万円 × 10% + 110万円」を計算した結果が給与所得控除額です。
自分の給与所得控除額を確認する方法
自分の給与所得控除額を知りたい場合は、翌年1月末ごろまでに勤務先から受け取る源泉徴収票を確認しましょう。
給与所得控除額ではありませんが、源泉徴収票で「給与所得控除後の金額」を確認できます。源泉徴収票の「支払金額」が給与などの収入金額に該当するため、「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を引けば、給与所得控除額がわかるでしょう。
源泉徴収票について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
給与所得控除と他の所得控除の違い
給与所得控除は、個人事業主などのように必要経費を引くことができない給与所得者のための制度であるのに対し、所得控除は条件を満たせばどの所得者も受けられる可能性のある制度です。また、給与所得控除は(給与)収入から引くのに対し、所得控除は所得から引く制度である点も異なります。
所得控除の種類は、以下のとおりです。
・雑損控除
・医療費控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・寄附金控除
・障害者控除
・寡婦控除
・ひとり親控除
・勤労学生控除
・配偶者控除
・配偶者特別控除
・扶養控除
・基礎控除
適用対象者や控除額が主な違いとして挙げられます。例えば、「基礎控除」は合計所得金額が2,500万円以下の納税者であれば、誰でも適用できる所得控除です。合計所得金額に応じて、16〜48万円の控除額を適用できます。
確定申告・年末調整の計算で給与所得控除が重要
給与所得控除は、確定申告や年末調整の手続きで所得税額を計算する際に重要な役割を果たします。
確定申告とは、1年間に生じた所得とそれに対応する所得税額を計算して確定する手続きのことで、年末調整とは源泉調整された所得税額と本来の税額の差を調整するための手続きのことです。詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
一歩間違うと、ペナルティの対象にも!確定申告の手順を図解【2024年版】
年末調整とは所得税の過不足の調整作業!確定申告との違いも解説
給与所得控除を使った給与所得の計算方法
給与収入が720万円の会社員、Aさんのケースを使って、給与所得を計算してみましょう。
まず、Aさんの給与収入金額(720万円)を把握し、表と照らし合わせて給与所得控除額を計算します。今回は「6,600,001円〜8,500,000円」に該当するため、給与所得控除額は182万円(720万円 × 10% + 110万円)です。
続いて、給与収入金額(720万円)から先ほど算出した給与所得控除額(182万円)を引きます。よって、今回の給与所得額は538万円です(720万円 − 182万円)
なお、各要件を満たす場合は、基礎控除といった所得控除を所得からさらに引けます。
給与所得控除・給与所得に関する注意点
給与所得控除や給与所得について、以下の点に注意しなければなりません。
・給与収入額が660万円未満の場合は使用する表が異なる
・給与所得控除以外に特定支出控除も認められている
・総所得金額計算時は給与所得から所得金額調整控除を引く
ここから、各注意点を解説します。
給与収入額が660万円未満の場合は使用する表が異なる
給与収入額が660万円未満で給与所得を計算する際は、使用する表が異なる点に注意しましょう。
本来、給与所得は給与収入額から、先ほど紹介した表を使って計算した給与所得控除額を引いて計算します。ただし、給与収入額が660万円未満の場合は、「所得税法別表第五」で給与所得の額を求めます。
例えば、給与収入が558万円の場合は「5,580,000円以上5,584,000円未満」に該当するため、給与所得控除後の金額は「4,024,000円」です。
給与所得控除以外に特定支出控除も認められている
給与所得者には、給与所得控除以外に特定支出控除が認められていることも覚えておきましょう。
特定支出控除とは、通勤費や転居費といった特定の支出が給与所得控除の2分の1相当を超える際に、超える分の金額を給与所得控除後の所得から引ける制度です。ただし、特定支出控除を受けるためには、給与所得者でも確定申告の手続きをしなければなりません。
総所得金額計算時は給与所得から所得金額調整控除を引く
給与所得者は、総所得金額を計算する際に、給与所得から所得金額調整控除を引ける場合があることも理解しておきましょう。
所得金額調整控除には、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」があります。控除額や対象者などについては、以下の記事を参考にしてください。
簡単に給与所得を計算するには?
給与収入が660万円未満の場合、「所得税法別表第五」に記載されている数字を確認すれば給与所得がわかるため、給与所得控除額を計算する必要はありません。また、給与収入が660万円以上の場合でも、以下の表にあてはめれば給与所得控除額を計算せずに給与所得金額を求められます。
| 給与などの収入金額 | 給与所得額 |
| 6,600,000円〜8,500,000円未満 | 収入金額 × 90% − 1,100,000円 |
| 8,500,000円〜 | 収入金額 − 1,950,000円 |
国税庁のホームページの「No.1410 給与所得控除」に掲載されている計算ツールを利用すれば、さらに簡単です。「給与収入の合計額(令和2年分以降)」の欄に金額を入力することで、給与所得がすぐに表示されます。
給与所得控除と103万円の壁の関係
103万円の壁とは、所得税がかかる年収(給与収入)のラインのことです。例えば、給与収入が103万円以下であれば所得税が発生しません(ほかに収入はないものとする)。
2024年11月30日時点で、給与所得控除の最低額である55万円と、基礎控除額の48万円を合計した金額が103万円の壁の根拠とされています。基本的に、合計所得2,400万円以下の納税者は基礎控除48万円の適用対象です。
なお、今後基礎控除の額を引き上げられることがあれば、壁のラインが「103万円」より大きい金額となります。
給与所得控除とは給与収入から控除できる金額
給与所得控除とは、給与所得を算定するにあたって給与収入から引ける金額のことです。収入に応じて、控除額が決まります。
給与収入が660万円「未満」か「以上」かによって、給与所得の求め方が異なる点に注意が必要です。給与収入が660万円未満の場合には、「所得税法別表第五」に記載されている数字を確認します。
自分の給与所得控除がどれくらいなのか気になる場合は、勤務先から受け取る源泉徴収票を確認してみましょう。「支払金額」から「給与所得控除後の金額」を引いた金額が、給与所得控除額です。
参考:国税庁「No.1410 給与所得控除」
参考:国税庁「No.1400 給与所得」
参考:国税庁「No.1199 基礎控除」
参考:e-Gov 法令検索「別表第五 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」
参考:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」
ライター:Editor HB
監修者:高橋 尚
監修者の経歴:
都市銀行に約30年間勤務。後半15年間は、課長以上のマネジメント職として、法人営業推進、支店運営、内部管理等を経験。個人向けの投資信託、各種保険商品や、法人向けのデリバティブ商品等の金融商品関連業務の経験も長い。2012年3月ファイナンシャルプランナー1級取得。2016年2月日商簿記2級取得。現在は公益社団法人管理職。